03.01.11: JR武蔵野線への愚痴
あ、またこんどって書きつつ写真掲載してなかったですね、またこんど!
で、今日の話題はJR東日本の武蔵野線ネタ。年末のある日、205系の5000番台に乗りました。これはもともと山手線にE231系が投入されてあぶれたものが武蔵野線に来たもので、今期は取りあえず8連2本。なぜ5000番台で区分しているかというと、なんと界磁添加制御からVVVFに改造されているからなんです。山手線でくたびれた車体(実際、シートなんかかなりへたっていたし、運転室なんかもあちこと塗装が剥げていた)とVVVFのステップレスな加速感とサウンドがなんとも不釣り合いで面白かった。それにしてもVVVF化改造の理由が不思議。武蔵野線は京葉線と直通運転しているため京葉トンネルを通過するのですが、ここを通過する車両は1ユニット故障でも自力でトンネルの勾配を上れなければならない。そのため従来の武蔵野線用205系は8連でも6M2Tという贅沢な編成でした。が、山手線の余剰車の関係からM車はあまり数がなく、6M2Tは組めない。そのため粘着特性に優れるVVVFにしてこの条件をクリアしようという算段らしい。しかし制御系(モーターも?)全部とっ換えるかねえ・・・。
いずれにせよ武蔵野線103系の205系化はどんどん推進して欲しい。なにしろ長いトンネルを高速で走行するもんで、103系だと騒音がひどくって・・・。地下鉄よりも速度が高いぶん始末が悪い。ホントにうるさいんです。知り合いと乗っていても、トンネルにはいると会話はストップです。(´ヘ`;)ハァ
03.01.11:欧州出張レポート
またこんど、って言っていてまた忘れそうだからなんとか欧州出張時の写真でも載っけときましょう。
11月前半の出張はワシントン~LAでしたが、後半は欧州の旅。スイス(ジュネーヴ)~フランス(ベルフォルト)でした。で、今回鉄道に乗れたのは仕事を終えての帰り道、フランスのムールーズ(日本人はミュールーズというが、向こうでは皆ムールーズという)からBaselまで。なぜ目的地のベルフォルトからではなくムールーズからかというと、そこには鉄道博物館(下記パンフがそれ)があるらしいという情報を事前にキャッチしていたので、短い自由時間を活用してそこに寄ってみようと考えたのだ。仕事で顔なじみとなったドイツ人のThomasに(機関車じゃないよ!)車でムールーズまで連れて行ってもらい、そこから博物館へ行こうという作戦だった。が、しかし世の中そううまくいくもんじゃない。駅で博物館の場所を聞いてみるとバスに乗ってしばらく行かねばならないとのこと。こちらはでっかいスーツケースを持っているので、まずは駅に預けようかと思ったら今日は休みで預かれない。バスもあまり本数がない、云々で結局あきらめてしまった。(実は行きにフランスのシャルル・ドゴール空港で一度トランジットをしくじってしまったため、若干慎重にならざるを得ない状況にあった)
ということで、今回は泣く泣く鉄道に乗車することで満足することにした。
上の写真は左からBaselまでの列車と車掌さん(この車掌、Baselでビールのんでたけど、ヨーロッパだからいいのかな?)、その車内、駅で見かけたEL、線路の内側にあった保安装置の地上子とおぼしき物体、駅で見かけたすごいスタイルの車両の連結面。新幹線みたいなもんかな?と思ってその前後をみたらなんと2両編成だった。がくっ!
下の写真、左から、木製の枕木なのにロングレールの溶接面(ん?フランスじゃ気温の変化が少ないのか木の枕木でもロングレールが使えるのか?、Basel駅、ヨーロッパだなあ、ヨーロッパ名物のtram。これもBaselにて。あ~、モロ、「世界の車窓から」の世界ですなあ。で、最後にムールーズ鉄道博物館のパンフです。
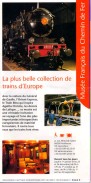
03.01.18:またも武蔵野線ネタ
武蔵野線は東京の外環状線的要素があるため、いくつかの線区にまたがった快速が運転されております。大宮から河口湖や鎌倉に行くものとか、八王子から日光へいくものとか。で、毎日数本ですが走っているものとして「快速むさしの号」というのがあります。これはその昔「新幹線リレー号」と言われていたもので、もともとは八王子から大宮までを中央線、武蔵野線、武蔵野貨物線を使って直通させていたものが改名されたものです。で、改名後もずっと三鷹区カラーの165,169系が3+3の6連で運用されており、私もたまにこれに乗れるとついているような気分になったものですが、12月からなぜか中央線カラー(ということはスカ色)の115系が運用されるようになってしまった。これってなにかえらくレベルダウンしてしまったような気がします。①2ドア、デッキ付き→3ドア、デッキなし(冬寒く、夏暑い) ②簡易リクライニング、クロスシート(一部固定向かい合わせ)→ロングと固定向かい合わせのセミクロスシート ③台車がDT32→DT21とマクラバネがダイアフラム式エアサスからコイルバネに格下げ ④床の遮音仕様も違うみたい、騒音が大きいように思える。 休日の快速は余剰になった183系(古いとはいえ、かつての特急車両)が運用されているそうなので、むさしの号にも回してほしいな、無理か・・・。
そう言えば、また(!!)先日武蔵野線が全線に亘って止まった。理由は越谷の方で枕木が燃えたから。どうして遙か彼方の出来事のために全線止めるかなあ? もう少し旅客はサービスだって気持ちできめ細かにシステムを考え直して欲しいな。私鉄だったら絶対こんなことはないでしょ?だいたい台風でも雪でもJRはすぐ止めちゃうよね。併走している私鉄は何事もなく運転しているときでも・・・。このへんがまだまだ親方日の丸時代の名残なのかね?
03.09.08 :ベルギー、鉄道の旅
半年以上ご無沙汰しちゃいましたが、その罪滅ぼしじゃないけど、じゃーん、特別版ですよぉ~、世界の車窓から、ベルギー編。
まずはブラッセルの地下鉄から。 第3軌条式。2~4両程度。車内は対座シートでドアは自分でハンドルを引くとエアで開くタイプ。ステンレス車体で車体端部は明るいオレンジ色。どうもステンレスは車側スキンのみで鋼製部分をオレンジにしているように思えます。料金は券売機で前もって買います。所要時間によるゾーン区分のようです。路線表示にいま電車がどこの駅にいるという表示がでるのでまあまあ親切。ホーム白線の内側に盲人用とおぼしき金属製の滑り止めが設置されています。上にのるとかちゃかちゃと音がした。車両の台車はちょっと見にくいけど左の枕バネがコイル2本のものとエアサスのものとがありました。たぶん全電動車なんでしょうね、加速はスムーズでかつかなり加速度は高めでした。(日本の地下鉄より全然加速がいい。これはワシントンDCでもオフェンバッハでも感じた。)
それでは続いてベルギー国鉄(たぶん)編。と言ってもBrusselsからAalstまで移動しただけなので、ネタは少ないんですが・・・。
駅の行き先表示は空港みたいにたくさん表示してます。この左にも同じ大きさの表示があり、24列車ぶんくらいが表示されています。ちなみにあまり時間は正確ではないらしく、私が乗った電車も5分くらい遅れてました。(ましな方?) やってきた電車は1M2Tの3両編成。最後尾がM車なんですが、なぜかZ型のパンタは先頭車についてました。車体とプラットフォームとの高低差はご覧のようにかなり大きくステップ3段分ありました。客室ドアは回転するポールにアームが付いたプラグドアで、これは地下鉄もそうだったかな。客室ドアはご覧のように車掌がキーでロックを解除して身近なドアからボタン操作で開けました。台車は仏独混成みたいな感じで、トレーラーはミンデン風、電動車はアルストーム風でした。(以前見て感じたのは台車はほんとに各国はっきりしているということで、フランスはアルストームばっかり、ドイツはミンデン・ドイツばっかりでした。日本は?最近はボルスタレスの切り張り細工みたいなちゃちなものが主流になってしまいましたね。) そうそう、列車の走りは、というと地下鉄とは正反対で、加速は昔の客車列車なみにとろくて驚きます。減速も同様で、減速時の音も客車そのもののシャーという音がします。ただクルーズ速度はそれなりに高いようです。レールのジョイント通過音はほとんどきこえず、ロングレールになっているようですね。
はい、それではベルギーだより、この辺で失礼します。
03.10.12 :書籍ご紹介
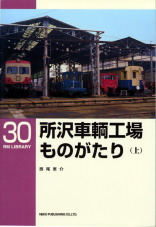
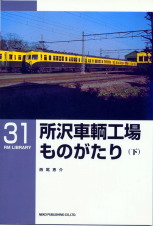 先日珍しい本を見つけてうるうるしつつ帰ってきました。これです、じゃ~ん! 西武所沢車輌工場と言えば西武(ライオンズじゃないよ)ファンなら誰でも知ってる、関東の大手私鉄では唯一自社で車輌生産を行っていたユニークな車輌工場です。
先日珍しい本を見つけてうるうるしつつ帰ってきました。これです、じゃ~ん! 西武所沢車輌工場と言えば西武(ライオンズじゃないよ)ファンなら誰でも知ってる、関東の大手私鉄では唯一自社で車輌生産を行っていたユニークな車輌工場です。時代の流れとともにその役割を終えたと聞いていましたが、まさかこんな風に資料としてまとめた本がでていたとは・・・。(‥、)、
私が物心ついたころには西武のカラーはすでにファンの間で赤電と通称されるくすんだローズとベージュのツートンになっていましたが、この本ではそのずっとずっと前から(工場ができる前、第二次大戦後当時)説明されていて、ページ数は少ないですが、貴重な写真も含まれていて、頷くことしきり。
あと一緒に「なぜ起こる鉄道事故」(こっちは交通安全の仕事の参考にもなる)という本を買いましたが、貨物とか客車列車の一番後ろにつながれていた車掌の乗っている車輌、緩急車と言って「フ」の記号がついていますが、あれがもともとブレーキをかけるためにつながれていた車輌で「フ」はブレーキのブの濁点を取ったものだということを初めて知りました。
03.12.03: 久々の西武線の旅
先日、久々にせき歯科医院へ行き、その際にここのところ都営大江戸線利用が増えて使わなくなって来ていた西武池袋線に乗った。
歯科医院は池袋からたった3つめの江古田という駅の近くにあり、そこまでの乗車だと自分が江古田に住んでいた頃とあまり施設も車輌も変わりばえがしないような気がしていた。(各停だとあまり新しい車輌の出番もないようだし)
で、今回はまったく無駄な遠回りで帰ることにした。上りで池袋に戻るのではなく、下りで秋津から通勤で使う武蔵野線を経由して帰る、なんてのはどうだ? てなことで、江古田からまずは下り各停に乗る。
来たのは豊島園行き各停。車輌はやはりいまや古株の101系。江古田を出てびっくり。ここまではほとんど変わらなかった景色ががらりと変わる。しがない地上の通過駅だった桜台は高架線上の駅となり、近代的な面もちとなって全く私の知っている駅の面影はない。下りに乗ってみて正解。そのまま練馬駅へ。ここで豊島線は分岐になるため本線に乗り換える。
今度は準急が来るらしい。やった!ようやく最新の20000系に遭遇。西武初のワンハンドルコントローラーで、ようやく私鉄の最新水準に追いついたと思える車輌が西武からも出てきた。走り出すと加速も3.0Km/h/sの公表値に違わずそこそこ良い。で、驚いたのが速度。西武は鈍足、という先入観があったが、いつのまにか池袋線も制限が上げられたようだ。何気なく100km/hまでは出すようになっていた。へええ・・・。(それでもいつも乗っている京王線の加速度3.3、最高速115km/hと比べては可哀想だが・・・)ただ、20000系で笑っちゃうのが走行時に両開きの客室ドアが発するパタパタという音。これっていにしえの551,701,801,411系あたりが使っていたけど耐久性の関係で長持ちしなかったアルミ・ハニカムドア(アルミの蜂の巣状の構造が中に入っている軽量ドア)とまったく同じ音じゃん。その後の車輌はみな101系以来のステンレス・プレス・ドアでこんな軽い音はしなくなっていたのに・・・・。
石神井公園で今度は急行に乗り換える。来たのは2000系かあ、と思って車内に入ってからプレートをみたら9000系だった。カッコは同じでも2000は界磁チョッパの回生制動、9000は廃車になった101系の廃品活用による抵抗制御。どんなもんかな?それにしても車輪踏面の荒れによると思われるごろごろ音がひどいな。これもVVVFインバーター+回生制動みたいな付随社遅れ込め(回生ブレーキ効率を上げるためにモーターなしの車はできるだけブレーキをかけないよう、エアの充填を遅らせる)がないためにクハでもフルにブレーキを使うせいかな? でも9000系として更新された際にフラット防止装置が付けられたって書いてあったけど?? いつもの常で電流計を眺める。ん? やたら針の動きが早い。101系と基本的に同じはずなのに・・・・。もしかして9000では101系ではブレーカーで切り替えることができた高加速設定(たぶんカム軸式制御器モーターを早く回すだけ)が常時使用になっているのかも。で、ごろごろとうるさかったけど、速度はやはり昔よりは高くて、100km/hは出すようになっていた。いやあ、進歩進歩。これは101系以前の車輌が混在していたらあり得なかっただろうな。
ここで一つ失敗。降りようと思っていた秋津は急行では止まらないのだった。で、所沢まで行ってしまった。さて、どうするか?
①各停で一つ戻って秋津から武蔵野線 ②池袋線で池袋へ戻る ③新宿線で西武新宿へ
迷った末③のオプションを選んだ。来たのは2000系の急行。新宿線も高速化されたのかな?と期待しつつ乗ったが、残念、こちらも高速化はされているようだが、最高速は90km/hのようだ。あまりぱっとしない走りで西武新宿に着いてしまった。
それじゃあ帰りの京王線で口直しでもするか、と思っていたが、なんだか疲れて、京王線では中間車の座席で眠る、ごく普通の乗客に成り下がってしまったヤマケンでした。