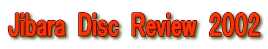
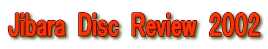
Vol.11
・芸術の秋、食欲の秋、なんて言うけれど、最近の私にとっては「秋眠、暁を覚えず」と言う感じ。眠い!
Live from New York City, 1967 / Simon & Garfunkel
 今頃になってこんな音源が出てきた。蔵出し音源ってやつでしょうか?一部の曲は企画盤にすでに収められていて、その全貌があらわにされることがファンの間では望まれていたものらしい。文字通り67年のNYでのライヴ。メンバーは二人だけでバックはなし。(他のライヴではしっかりスタジオ系を中心としたサポートが入っていたりしたから、ようやく二人でのライヴの音をたっぷり聴けるアルバムが登場した、という思いのファンもいるのかな? ポール・サイモンのギターはさすがにアイデアといいテクニックといいすばらしいものがあり、ガーファンクルの歌声とMC(短いけど、客席との一体感を強める不思議なマジックがある)、どちらとも当時のS&Gのライヴがどうだったかを知るのには十分以上のものがあって楽しい。音質は今のリマスター技術をフルに駆使すればもっともっといいものになったんじゃないかと思うが、そうしなかったのも一つの見識なんだろうな。
今頃になってこんな音源が出てきた。蔵出し音源ってやつでしょうか?一部の曲は企画盤にすでに収められていて、その全貌があらわにされることがファンの間では望まれていたものらしい。文字通り67年のNYでのライヴ。メンバーは二人だけでバックはなし。(他のライヴではしっかりスタジオ系を中心としたサポートが入っていたりしたから、ようやく二人でのライヴの音をたっぷり聴けるアルバムが登場した、という思いのファンもいるのかな? ポール・サイモンのギターはさすがにアイデアといいテクニックといいすばらしいものがあり、ガーファンクルの歌声とMC(短いけど、客席との一体感を強める不思議なマジックがある)、どちらとも当時のS&Gのライヴがどうだったかを知るのには十分以上のものがあって楽しい。音質は今のリマスター技術をフルに駆使すればもっともっといいものになったんじゃないかと思うが、そうしなかったのも一つの見識なんだろうな。
Live in Tokyo / Hughes Turner Project
live_in_tokyo.jpg) 会社&中学の先輩でありただいまアメリカに単身赴任中のさりー(♂)の美人妻に誘われて渋谷へ聴きに行ったライヴです。今さら説明不要かもしれないけど、第三期ディープ・パープルのベース&ヴォーカルだったグレン・ヒューズとレインボーのヴォーカルだったジョー・リン・ターナーのジョイント・プロジェクトの日本公演ライヴ。二人をサポートするのは3人の日本人。梶山章(G)、永川敏郎(key)、工藤義弘(ds)。 先にリリースされている二人のプロジェクトのアルバム、HTPからの選曲が中心かと思えばそうでもなくて二人のソロやそれぞれがこれまでに関わってきたバンドのオハコも織り交ぜ、ファンサービスに徹しているという感じ。そう言う意味ではそれぞれのソロを知らない人も、HTPのアルバムを聴いたことにない人もみんな楽しめるお楽しみアルバムと言えるか・・・。
会社&中学の先輩でありただいまアメリカに単身赴任中のさりー(♂)の美人妻に誘われて渋谷へ聴きに行ったライヴです。今さら説明不要かもしれないけど、第三期ディープ・パープルのベース&ヴォーカルだったグレン・ヒューズとレインボーのヴォーカルだったジョー・リン・ターナーのジョイント・プロジェクトの日本公演ライヴ。二人をサポートするのは3人の日本人。梶山章(G)、永川敏郎(key)、工藤義弘(ds)。 先にリリースされている二人のプロジェクトのアルバム、HTPからの選曲が中心かと思えばそうでもなくて二人のソロやそれぞれがこれまでに関わってきたバンドのオハコも織り交ぜ、ファンサービスに徹しているという感じ。そう言う意味ではそれぞれのソロを知らない人も、HTPのアルバムを聴いたことにない人もみんな楽しめるお楽しみアルバムと言えるか・・・。
ところで、これを見に行ったときに感じた中のひとつに、グレンのベース機材が決して過去の歴史の上に踏みとどまっておらず、5弦ベースやH&Kのアンプに代表されるようにベーシストとしても現代の歩みを止めていないんだな、というちょっと意外なことでした。グレンのヴォーカル?相変わらず情感豊かにすばらしい表現力でした。
RIT's House / Lee Ritenour
 毛並みのいいジャズをルーツとしたフュージョンギタリスト、という雰囲気を感じさせるリー・リトナーの最新作。。ラリー・カールトンがその風貌とともに(?)どんどん土臭いルーツを露わにしていくのに対し、こちらはいつもながらにいたって着飾るのを忘れないというかおしゃれに気を配っているという感じ。その辺が最近はプロデュースを他に任せてギタリストに徹しているラリーと自分のアルバムはもちろん、人のアルバムのプロデュースのみならずディレクションにも手を出している(社っ長さんですからな!)リーとの違いにも現れていると思う。
毛並みのいいジャズをルーツとしたフュージョンギタリスト、という雰囲気を感じさせるリー・リトナーの最新作。。ラリー・カールトンがその風貌とともに(?)どんどん土臭いルーツを露わにしていくのに対し、こちらはいつもながらにいたって着飾るのを忘れないというかおしゃれに気を配っているという感じ。その辺が最近はプロデュースを他に任せてギタリストに徹しているラリーと自分のアルバムはもちろん、人のアルバムのプロデュースのみならずディレクションにも手を出している(社っ長さんですからな!)リーとの違いにも現れていると思う。
ということで、聴く前から想像できるようにいい音で、整ったアレンジ。フュージョンファンの求めるものを入れておくことを忘れずに、かつスムース・ジャズFM局でのオン・エアにも適したというような良くも悪くも八方美人的なジャズ寄りギター・フュージョンアルバム。
Celtic Odyssey (Narada collection series) / V.A.
 少し前からアイリッシュ、ケルト系に興味をいだいていて、たまたま出張時に宇都宮の書店で音楽之友社から発行されていた(知らなかった)文字通り「アイリッシュ&ケルティック・ミュージック」という本を参考書みたいに眺めているのだが、たまたま八王子のタワレコのワゴンにこんなのがあったので買ってみた。アルタン、カパー・ケリーシリーズ、など「参考書」にのっていてある程度背景がわかるミュージシャンもいるのだが、大半についてはわからず。う〜ん、高くてもありがた迷惑なくらい懇切丁寧な解説のついている国内盤を買うべきなんだろうな、本当に掘り下げたいのであれば・・・。ちなみにこのアルバムは既にNARADAのカタログからは消えてしまっているようでした。(だからワゴンにあったのね)
少し前からアイリッシュ、ケルト系に興味をいだいていて、たまたま出張時に宇都宮の書店で音楽之友社から発行されていた(知らなかった)文字通り「アイリッシュ&ケルティック・ミュージック」という本を参考書みたいに眺めているのだが、たまたま八王子のタワレコのワゴンにこんなのがあったので買ってみた。アルタン、カパー・ケリーシリーズ、など「参考書」にのっていてある程度背景がわかるミュージシャンもいるのだが、大半についてはわからず。う〜ん、高くてもありがた迷惑なくらい懇切丁寧な解説のついている国内盤を買うべきなんだろうな、本当に掘り下げたいのであれば・・・。ちなみにこのアルバムは既にNARADAのカタログからは消えてしまっているようでした。(だからワゴンにあったのね)
Sacred Hills / Char
 チャーの最新作はギター・インスト。チャーのことだからもちろnフュージョンなどではなくロックギター。ほとんどがチャーとジム・コプリーの二人で作られ、一部サポートミュージシャンが参加している。どれをとってもいいギターの音が聴ける。最近マッチレスからヒュース&ケトナーに代えて、このアルバムはそれに弾かされた感もあるそうだ。ホントにいい音だ。ワールドカップに日本中が連日連夜一喜一憂していたときに平日の22時前にニュースステーションのテーマとして流れてきた曲も収められている(構成は違うように思える)が、その時のことを思い出して、なんだかずいぶん前のことのように感じてしまった。それにしてもなんだか風景を感じられて、いいアルバムだなあ。
チャーの最新作はギター・インスト。チャーのことだからもちろnフュージョンなどではなくロックギター。ほとんどがチャーとジム・コプリーの二人で作られ、一部サポートミュージシャンが参加している。どれをとってもいいギターの音が聴ける。最近マッチレスからヒュース&ケトナーに代えて、このアルバムはそれに弾かされた感もあるそうだ。ホントにいい音だ。ワールドカップに日本中が連日連夜一喜一憂していたときに平日の22時前にニュースステーションのテーマとして流れてきた曲も収められている(構成は違うように思える)が、その時のことを思い出して、なんだかずいぶん前のことのように感じてしまった。それにしてもなんだか風景を感じられて、いいアルバムだなあ。
Grapevine / Metro
 ええっ? もうMETROの新作が? METROとはチャック・ローブ(G)、ミッチェル・フォアマン(key)のコンビにウルフギャング・ハフナー(ds)そしてベーシスト(毎回のように交代)が加わった4人組のフュージョン・ユニットだが、個人的にはチャックにとってのスムース・ジャズばかりつくって「溜まって」しまっているものを「抜ける」空間だと解釈している。実際、ここでのチャックは他ではまず聴かれないようなディストーションでの「伸ばした」プレイを披露しており、曲想もソロ作やプロデュース作品では聴かれないようなハードなものが多い。
ええっ? もうMETROの新作が? METROとはチャック・ローブ(G)、ミッチェル・フォアマン(key)のコンビにウルフギャング・ハフナー(ds)そしてベーシスト(毎回のように交代)が加わった4人組のフュージョン・ユニットだが、個人的にはチャックにとってのスムース・ジャズばかりつくって「溜まって」しまっているものを「抜ける」空間だと解釈している。実際、ここでのチャックは他ではまず聴かれないようなディストーションでの「伸ばした」プレイを披露しており、曲想もソロ作やプロデュース作品では聴かれないようなハードなものが多い。
各メンバーが多忙なせいかユニットとしてのアルバムのインターバルは長く、ファーストの後は続編が長らく出なかったため、てっきり一過性のセッションだったのかと思ったくらい。しかし今回は一年くらいのインターバルで新作が登場した。これは画期的だ。で、またしてもこの作品ではベーシストが交代しており、メル・ブラウンという人になった。この人の流派はもろにウィル・リー派とでもいって差し支えのないような音であり、ということはMETROで初めてのスラップ系ベーシストとなる。アルバムとしての特徴は、いつものローブ、フォアマンによる作風の曲にサンプリングなどのサウンドをまぶし、元気なスラップ系ベースサウンドをボトムに配したという感じ。ただしボトムと言ってもウィル的な高音でのフレーズも随所に聴かれるため、これまでに比べるとベースの重心は高いように思えた。ま、しかしMETROである。いつもながらに私の期待は裏切ることはないようだ。
Brazilian Dreams / Paquit D'Rivera featuring New York Voices & Claudio
Roditi
 パキート・デリヴェラのことはそれほど詳しく知らない。キューバ人のサックス奏者でジャズとフュージョンの間を行き来している人かと思っていた。が、実際にはもっと間口の広い人らしく、クラシックまで足を伸ばしているようだ。本作品の特徴はコーラスグループのNYヴォイセズをフィーチャーしたこと。正直、私はそれで買ってみる気になりました。
パキート・デリヴェラのことはそれほど詳しく知らない。キューバ人のサックス奏者でジャズとフュージョンの間を行き来している人かと思っていた。が、実際にはもっと間口の広い人らしく、クラシックまで足を伸ばしているようだ。本作品の特徴はコーラスグループのNYヴォイセズをフィーチャーしたこと。正直、私はそれで買ってみる気になりました。
で、内容ですけど・・・、う〜ん、予想していたよりもさらにジャジーすぎて、ちょっと好みと違ったな。(買うときにNYヴォイセズをLAヴォイセズと勘違いしてたし・・・)
Perpectual Motion / Dave Weckle Band
 元チック・コリア・エレクトリック(とアコースティック)・バンドの、という冠はもはや必要のないフュージョン界屈指のドラマーといえるデイヴのバンド名義の最新作。全作からギターのバジー・フェイトンが脱退し、(というかギャラ関連で解雇?)フロントはブランダン・フィールズ一人となった。本作もその継承であり、ギタリストのメンバーはいない。
元チック・コリア・エレクトリック(とアコースティック)・バンドの、という冠はもはや必要のないフュージョン界屈指のドラマーといえるデイヴのバンド名義の最新作。全作からギターのバジー・フェイトンが脱退し、(というかギャラ関連で解雇?)フロントはブランダン・フィールズ一人となった。本作もその継承であり、ギタリストのメンバーはいない。
曲想は相変わらずメカニカルでテクニカル、かつグルーヴも、という感じの、これまでの同バンドの延長線上にある音。これまでの音が好きだったら「ハズレ」にはならんでしょう。
流宇夢サンド / 松原正樹
 当時のクロスオーバーファンなら聴いたことはなくともその存在くらいは知っているであろう、松っつぁんのファースト・ソロ・アルバム。そのころ私は早大のESSのミュージカルのバックをやっていて、その時のkeyが長いつきあいの野口久和、ベースとドラムはプロの人だった。で、「このアルバムどうですか?」ってそのdsの人に聴いたら「あれはスタッフのコピーだ」って一蹴されてしまい、買うタイミングを逃してしまった。その後レコードは当然廃盤、’95にタワレコがゲリラ的にJapanese Fusion Warと称してNYオールスターズ・ライヴとか、今剛や土方隆行らのソロ作と一緒にCD化したことがあったが、その時ですら「スタッフ云々」が引っかかってしまって買いそびれ、このアルバムを持つことはなかった。最近松っつぁんの一連の作品がリマスター再発されたり、新作がリリースされたりしているが、この作品は一緒にリリースされることもないようだ。じゃあ、なぜ今ここに?ちなみにこれは中古じゃなくてちゃんと店頭で買いました。 その背景は?他の店舗にはないと思うが、タワレコ
当時のクロスオーバーファンなら聴いたことはなくともその存在くらいは知っているであろう、松っつぁんのファースト・ソロ・アルバム。そのころ私は早大のESSのミュージカルのバックをやっていて、その時のkeyが長いつきあいの野口久和、ベースとドラムはプロの人だった。で、「このアルバムどうですか?」ってそのdsの人に聴いたら「あれはスタッフのコピーだ」って一蹴されてしまい、買うタイミングを逃してしまった。その後レコードは当然廃盤、’95にタワレコがゲリラ的にJapanese Fusion Warと称してNYオールスターズ・ライヴとか、今剛や土方隆行らのソロ作と一緒にCD化したことがあったが、その時ですら「スタッフ云々」が引っかかってしまって買いそびれ、このアルバムを持つことはなかった。最近松っつぁんの一連の作品がリマスター再発されたり、新作がリリースされたりしているが、この作品は一緒にリリースされることもないようだ。じゃあ、なぜ今ここに?ちなみにこれは中古じゃなくてちゃんと店頭で買いました。 その背景は?他の店舗にはないと思うが、タワレコ渋谷(訂正)新宿店では’95リリースの時の在庫を最近¥1,000で店頭に置いているから。と言うわけで、はい、これは新品在庫、¥1,000デス。(これは新宿店だけのことかもしれない。八王子店で見た同じシリーズは定価だった!)
で、中味は・・・・・、たしかにスタッフっぽいかな・・・。その後の作品を聴いてしまうとやはり、ね・・・。