�@�{���J�݁I
�i�{���̔����q�|���l���[�g�͔@���ɁH�j
�@�����͔����q�̎���牡�l�̎��Ƃ֍s���̂ł����A��T�Ԃōs���ĉ������ɑ�a�Œ��肽�̂ŁA�����͑����ԕ��̔�Q���C�ɂȂ���d�Ԃōs�����Ƃɂ��܂����B���āA�ǂ�ȃ��[�g�ōs�������ȁH�@�������@�|�@�앐���@�|�@�������@�Ȃ�Ăǂ��ł��傤�ˁH�@�ł����܂苻����������d�Ԃ���Ȃ��ł��˂��B���ƌ����āA���l���@�|�@���l���k���@���Ⴀ��܂肾���E�E�E�E�B���͓S���̎��S�Ł@�i�q�@�d�Q�R�P�n�Ȃ�Č��ɍs���Ă݂����ł����E�E�E�E�A������Ɖ���肷����Ȃ��E�E�E�B
�@�����̂��Ƃ������ł����A���͗��T�l���ɏo���ŁA������̃L�b�v�i�V�����j����z���悤�Ƃ��āA�n�b�Ƃ����B���₢������Ɩʔ������[�g�͖������낤���H�@�Ƃ������ƂŁA���ǎd�����Ԃɂ���Ȃ��Ƃ���������킯�ɂ��s���Ȃ��̂ŏT���ɍl���邱�Ƃɂ��܂����B�����A�Ȃɂ�����Ă��ł��傤�ˁA���́E�E�E�B
�@�y��s�Ɏ����Ă������ǂݕ�
�@�Ƃ���ł����ł̓J�~�T���Ɨ��s�ɍs���Ƃ��͍s������œǂޖ{�����O���s�����悩�ŕK�����B�����ł����A��T�s�����y���̎��͑O���ɋߏ��̖{���Œ��B���܂����B���܂��܉��y�֘A�Ŗڂɕt�����̂����������������A�N���}���I�[�f�B�I���o�C�N���݂���ł����A���ǂ߂ڂ������̂Ƃ��Ĕ������̂��S���s�N�g���A���S�������̐����S�����W���S���t�@���T�����̂i�q�ʋΓd�ԓ��W�B
�@�����S���ւ̎v������
�@�����͎������Z���Ƃ���܂ʼn����ɂ������߂ɂ��Ȃ�v���o�Ƃ������v�����ꂪ�����Ĉ��̋L�������x���J��Ԃ��ǂ�ł��܂����B�Z�p�_����������[���̂����A��q��t�@���̗��ꂩ�犴���Ă������Ƃ�������Ă��镨�������[���A�w�̐i�����x�����ЂɊr�גႭ�����䂩�����Ƃ��i�T�Tkm/h�������Ă���Ǝ�O�ň�x�u���[�L�������A�T�Tkm/h�܂Ō������Ă����j�A�V�O�P�n�̂g�r�b�������O�i�܂莩����C�u���[�L����j�̊ɉ����������I�œƓ��������Ƃ��A���̎���ɏ���Ă����o���̂���l�Ԃɂ͂��܂�Ȃ����e���肾�����B�܂��Z�p�I�ɂ͐����͎v�������藧���x�ꂽ��Ђ������̂œ��}��c�c�̃t�@���̑O�ł͎ԑ̐�s���͂��Ă��邱�ƂƂ��A���ʂł͕����Ȃ����Ƃ��A�����ēݑ��Ȃ�����ό����}�����邱�Ƃ��炢�����ւ�邱�Ƃ͂Ȃ��������ǁA�ԗ��̃o���G�e�B�Ƃ����j�I���l�Ȃǂł͑��ɕ����Ȃ����̂��������B�i���͒��w���Ǝ��ɏ��������ɏA�E���邩������Ȃ��Ǝv���āA�����N���Ƃ��̂��Ƃ�̂������ԗ��ے������K�˂Ă��͂Ȃ����f�������Ƃ����邭�炢�B���̎��ɕ������̂́A���ۂ̎ԗ��̐v�̓��[�J�[�ɂ�点��̂ŁA�����ԗ�����肽���̂Ȃ烁�[�J�[�̕����I�X�X���ł���A�Ƃ̂��Ƃ������j
�@���āA���̓t�@���̗���������[�U�[�̗���̕��������̒��ŋ����̂ŁA��������̂P�O�R�n�̓g���l�����Łu���v�₩�܂����A���S�n�������A�~��̌̏�ɂ��x��̌����Ȃ̂ł������ƎR����Q�O�T�n�u�������̂����ڂ�Ղ��Ĕp�Ԃ�������ė~�������i�R����̂Q�O�T�n�u�������ɂ��P�O�R�n���ǂ��߂��邱�Ƃ�S�z����t�@���̐����G���ɂ̂��Ă������A���p�҂��炢�킹�Ă��炦�Ώ�k����Ȃ��I�j�A�������͎ԗ��̃o���G�e�B�����Ȃ��Ėʔ��݂Ɍ����邯�ǁA�����Đ��m�����A���S�n����������D���Ȃ�ł��B�ł��Ȃ����͎����̂Ȃ��ł͕ʊi���ȁH�@�ȑO�o���ōs�����Č��ŁA�ߍ]�S���̐�������̏��n�ԗ������������Ƃ��̂Ƃ��߂��͂Ȃ�Ƃ������Ȃ����̂����������E�E�E�B
�O�Q�D�O�S�D�O�V�F�@���l���ʂ�
�@���ǂ��̂��́@�������@�|�@�앐���@�|�@�������@�|�@���}���@�̗��ł����B�A�H�͑S���̋t���ł��B�ǂ����d�Ԃɂ��������炽�܂ɂ͍őO���i�^�]�Ȃ̂������j�ŗ����Ă������A�Ƃɂ킩�S���������C����Ă݂܂����B
�@�s���F�@
�@�E�������F�X�O�O�O�n�e��B���`��A�ǂ����Ȃ���}�������}�̂�����т����Ă��������������A�܂��ŐV�s�̂X�O�O�O�̉^�]���i�͂܂��݂����Ƃ��Ȃ���������A�܁A����ŁB���͂����d���v�����Ă��܂��̂ł����A�X�O�O�O�̂���̓����͂h�f�a�s���L�Ȃ̂��ȁH�N�����Ă��炭�͐j�����l�Ŏ~�܂��Ă�����ǁA�C���o�[�^�[���̎��g�����Ђ�[��Əオ���ď�������Ɛj���s�N�s�N��������C���ɂȂ�B���������̎��ɉ������ɓ��Ɉ�a���͂Ȃ��B�s�v�c�����E�E�E�B
�@�E�앐���F�ł���Q�O�X�n���߂ĂQ�O�T�n�Ƃ̊肢���ނȂ����匙���ȂP�O�R�n�������B���߂��������C�����������A�܂��s���悪����̂ł����m���r�������Ă���ꂸ��ނȂ���荞�ށB��H�������`�s�b�d�l�̂P�O�R�n�͂��Ƃ��Ɖ^�]�ȂƂ̎d�ɂ͈�ԉE�Ɉꖇ�K���X�������邾���ŁA�������^�]�����̋@��̒���o�����ٗl�ɑ傫���A�q�Ȃ���͂܂������^�]���i�͖ڎ��ł��Ȃ��B�p�����č��Ȃɍ���A�����̗��q�ƂȂ�B
�@�E�������F�@�X�O�O�O�n���ȁH�Əڂ����Ȃ��Ȃ�Ɋ��҂����������̂͂W�O�O�O�n�̋}�s�B���̓d�Ԃ����ƂȂ��Ă͂Ȃ�̓������Ȃ��d�ԂɂȂ���������Ȃ��B�������������烏���n���h���}�X�R���i���u���[�L�j�ƊE���`���b�p������̗p�������т͑傫���Ǝv���B�ŁA����o���ƁA���`��A����ς葬�����炷�̂ɔM�S����Ȃ��A�ƌ�����̂��킩��悤�ȋC������ȁA�債�����x����Ȃ��Ă������݂ȉ��h�ꂪ�����B��͂荂�����E������Ȃ���ȁB�i�ł���Ԃɂ���Ă͂P�O�Okm/h�o���Ă������j
�@�Ƃ���ŁA���̐���ɏ�Ԃ��Ă��Ėʔ��������͎̂ԗ������^�]�Ȓ���ɐw����Ă����u�I�^�N�v�������B������Ǝ���x�ꕗ�̂₽��傫���^�����ꂵ���V�����_�[�o�b�O��K�̌���ɂ�������đO�����Î����Ă���̂����A�ŏ��̈�w�͉������Ȃ������B���A�ٕς��N�������̂͂��̎��̉w�B�ׂ�ɏ�荞��ł����������Ȃ�ƒm�荇���炵�������S���������I�i�������I�I�j����܂Ŗ����������I�^�N���j�q�������Ȃ�吺�łȂɂ�炪�Ȃ藧�Ďn�߂�B���������Ă���̂��Ƃ�����Ǝ����X���Ă݂�ƁA�ǂ����ŋߓ��}�ł͒��Ԃɗ�Ԏ�ʕ\���i�}�s�Ƃ����ʂƂ��̂���j�̃o�b�N���C�g�������Ă���炵���A���ꂪ�C�ɓ���Ȃ��炵���B��������X�吺�ŕ���t���Ă���B�l�b�g��ł����ɂȂ��Ă���ƌ����Ă����B�͂�����Ƃ����������o���ė~������ȁI�Ƃ������Ă����B�͂͂́A����Ȃ��Ƃǂ��ł����������A���ł���ł������ƌ�����B�Ƃ����킯�ŁA���}�͎ԗ���H���̃C���v���b�V���������A���̓T�^�������J�b�v���̈�ۂ���c���Ă��܂����B
�@�E���}���F���������̓��̎��ɂƂ��Ĉ�Ԃ̂����������������ȁH�@�Q�P�O�O�n�������}�������B���₠�A�������Ă݂���������ł��悧�B�V�[�����X���̃C���o�[�^�[�𓋍ڂ����ԗ��͉������ɉ��K��t�ł�̂ł��B�u��`���ǂ�݂ӂ�����`�v���ĂȊ����ł��B��������̕��A������ɑ����Ă���d�T�O�P�n�Ƃ����̂�����Ȃ��������邻���ł��B�i�Ƃ����������炪��y�j�ŁA���̓d�ԁA������}�̉����Ȃ̂ł���Ȃ�̑�������҂���������ł����A���₢����҈ȏ�̑���ŁA���̉����̋������P�P�Okm/h�^�]�Ȃ�ŏ\�������Ȃ��A�Ǝv���Ă������A����ϋ��}�͕ʊi�̗l�ȋC�������B���i���獂���܂ł̉��������}�����Ƃł��������A�����Ȃ�ł���ˁB�łP�O�Okm/h�ȏ�Ńm�b�`�I�t�i���ēd�Ԃł����������H�j���鎞���A�܂��܂������r���ł��I�Ƃł������������ȕ��͋C�ł�����ˁB���܂��ɂ��̓d�ԁA�N���X�V�[�g�i�i�s�����Ɍ������č���^�C�v�̍��ȁj�ŁA�������^�]�Ȓ���Ɉ��A�S���}�j�A�₨�q����܂ɂƂ��Ă̓����Ȃ�����B�^�]�Ȃ̌㕔�̎d�̑��K���X���傫���Ď��E���������A�������܂�Ȃ��d�Ԃł����B�����������܁I���A���������C���o�[�^�[��������Ȃ����ĉ������̃��[�^�[�̉����Ȃ��Ȃ����͂������Ă������ł����B�i���ʂ̐l�ɂƂ��Ắu�₩�܂����I�v�Ƃ����]���ɂȂ�̂�������Ȃ�(^_^;)�j
�@�ŁA���Ȃ݂ɂ��̓��̕��H�ł����A�Ȃ�̌|���Ȃ����H�Ɠ������̂���Ȃ����ċA��܂����B
�O�Q�D�O�S�D�P�R�F�l���o�����|�[�g
�@�P�P���P�Q���Əo���ŕl�����班�����C���ʼn������Ƃ���ɂ���u�ٓV���v�Ƃ����Ƃ���ɍs���Ă��܂����B
�@���[�g�F�@���l���@�|�@���C���V�����i�����܁j�@�|���C�����@�ƂȂ�̕ϓN���Ȃ����[�g�ł����B���߂�Ȃ���(^_^;)�@���������ԗ������ɂ���Ƃ��������̂͂Ȃ��������ǁA���H�F�Q�O�T�n�@�|�@�Q�O�O�n�@�|�R�P�R�n�A�@���H�F�P�P�T�n�@�|�@�P�O�O�n�@�|�@�Q�O�T�n�i�R��j
�l�����ӂ̓��C���͌o�����Ȃ������̂ʼn^�]�Ȓ���ɂւ���܂������A�R�P�R�n�̓����n���h���E�}�X�R���A�R�l�R�s�A�i�r�V�X�e���t�������肪�����Ȃ낤���H�@�i�q�̎ԗ��͎����݂�����d���v���Ȃ��̂ł܂�Ȃ����A���̂����Ƀi�r�����Ă����B�E�E�E�������A����̓��e���ĕK�v�Ȃ��̂Ȃ̂��˂��H�H�����������[�^�[�ɒʓd���Ă���Ƃ��ɓd���Ԃ̎ԗւ̊G�����ʂɂȂ�����A�u���̉w��ԁv�Ȃ�ď����̍����̐��Ŋm�F������E�E�E�B���̓��e���āA����̐l�̒�Ă��Ⴀ�Ȃ��낤�Ȃ��E�E�E�B���������A���̔��ʂɂȂ�ԗ��̊G�����ǁA�R���̂l�Ԃ̃I���E�I�t�̕\���^�C�~���O�ɑ傫�����ꂪ����̂����炭�C�ɂȂ����B����ȂɎԗ��Ԃō�������̂��Ȃ��H�H����ƃm�b�`�I�t���ĉ���������Ă����炭���ʂ̂܂�܁A���Ă̂�������Ɓu�Ԃ�����ā`�i�l���قł����Ă݂܂����j�v���������܂��ˁB
�O�Q�D�O�T�D�Q�U�F�����̂ĂāA��������̂P�O�R�n�I
�@���������ł��B�@�S���t�@�����ŎR����̂Q�O�T�n���u�������ɂȂ�Ƃ����̂�m���āA���Ă������Ă������Ȃ��Ȃ�܂����B�ƌ����Ă��ʂɎR����𑖂�Q�O�T�n�ɖ���������̂ł͂���܂���B�C�ɂȂ�̂͂��̒ǂ��o���ꂽ�Q�O�T�n�̍s����ł��B�O�ɂ��������悤�Ɏ��̒ʋ̑��ł��镐������̂P�O�R�n�͕�������̒����g���l�����W�O�`�������鑬�x�ő���Ǝ����������Ƃ������ŁA�ׂ�ɍ������l�Ƃ̉�b���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��قǁB���������{�����Ă���Q�O�T�n�͂����ł��Ȃ��B�����Ń��}�P���͍l�����B�R����̂Q�O�T�n���������������I�ƁB
�@���������i�q�����{�̃T�C�g�ɃA�N�Z�X�B�������Ԃ�A�v�]��`����B��T�ԂقǂŕԎ��������B�ȉ��͂��̃R�s�[�ł��B
�����i�q�����{�Ȃ�тɂi�q�����{�z�[���y�[�W�������p���������܂��Ă��肪�Ƃ��������܂��B
���̂��т̂��ӌ��ɂ��܂��āA�ȉ��̂Ƃ�������Ă��������܂��B
��s���̓d�Ԃ̎�ւ��͐V������30�N���x�o�߂��Ă��鋌�^�d�Ԃ̎�ւ��𒆐S�ɐi�߂Ă��܂��B���₢���킹�̕�������ɂ��܂��ẮA���N�x���ɁA��������p�ɉ������s����205�n�d��2�Ґ���]�p����\��ł��B�Ȃ��A��������ւ�2003�N�x�ȍ~�������A205�n�d�Ԃ�]�p���A2005�N�x�ɂ�103�n�d�Ԃ����ׂ�205�n�d�Ԃɒu�ւ��\��ł��B
���̂��т́A�M�d�Ȃ��ӌ����肪�Ƃ��������܂����B
������A�݂Ȃ��܂Ɉ�����A�e���܂��i�q�����{���߂����Ă܂���܂��̂ŁA�������������ڎ���܂��悤��낵�����肢�\���グ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����{���q�S���������
�@���҂����Ⴂ�܂��B
�O�Q�D�O�U�D�Q�T�F�@�������̎v���o
�@�܂������������ł����B�ꃖ���Ԃ�ł��B
�@�킴�킴������`���ɗ���悤�Ȋ���Ȑl�͓��R�̂��Ƃ��d�Ԃ̐擪���ʼn^�]�m�̑���Ƃ���Ɋ֘A���镨�߂邱�Ƃ�������Ǝv���܂����A���Ă���Ȃ��ŕϒ|�тȉ^�]������̂ɏ����̂͂Ȃ��Ȃ��@��Ƃ��Ă͏��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�@�O�ɂ��G��܂����������ł������ȏ��N�����߂������͓̂����̐����r�ܐ������ŁA���R���̓d�Ԃ߂�@��ł����������킯�ł��B�ŁA�������ɂ͖��ȉ^�]������l�����������悤�ȋC�����܂��B�ǂ�ȉ^�]���Ƃ����ƁE�E�E�B
�@�ΏۂƂȂ�d�Ԃ͂P�O�P�n�ł����B�܂��A�������{�Ƃ����R�O�P�Ƃ��R�O�O�O�Ƃ����������Ƃ��Ǝv���܂����E�E�E�B���̉^�]���@�Ɋւ��邱�̓d�Ԃ̎�ȃv���t�B�[���Ƃ��Ắ@�@�J���������ɂ���R����i�E����ߕt���j�A�}�������t���B�������ʂ̃}�X�R���i�}���m�b�`�t���j�ƃu���[�L�̂Q�n���h�����Ń}�X�R���͍͗s�S�A�}���R�m�b�`�B
�ŁA���̉^�]�Ƃ́E�E�Ƃ���ŊF����A�������Ă����Ƃǂ�ȃC���[�W�ł����H�@�����A�P�`�Ȃ�ł��B���⌾�t��������Όo�ϐ��d���Ȃ�ł��B����Ƃ����̂����̋}���ȗ��q���A�b�v�ɑΏ����邽�߂Ɏ����ʂƈ�����@����Ȃ���������ȍ��S���������ԗ��╔�i��L�����p���A�Ƃ������ԗ����𑝂₷�̂ɕ��S�������߂Ȃ�ł��B�������A�����ł̕ςȉ^�]�ɂ��P�`�����Ă܂���Ă��܂����B�P�O�P�n�̃}�X�R���͂P�C�Q������A�R������`����A�S������ɊE����߂��g����悤�ɂȂ��Ă���̂ł����A�Ȃ��Ȃ��S�m�b�`�܂Ŏg���l�����Ȃ�������ł��B��������Ǝ����Ɨ�Ԃ̑��x���オ�炸�A�K���o���Ăn�m�������Ă��V�Okm/h���ւ̎R�ł����B�Ƃ��낪���܁`�ɂS�m�b�`�܂œ����l������ƁA�E����߂̉�H�ɓ���A�Ƃ���ɑ傫�ȓd���v�̐j�̐U���ƂƂ��ɉ������n�܂�A�X�O�����^�����炢�܂ł͂Ȃ�̃X�g���X���������ɉ����������̂ł����B�������A���̂Ƃ��d���v�͂O�D�W���`���x�܂ŐU��A����Ȃ�ɓd�͏���������Ƃ���Ă��܂����B���Ƃ��ƒ������J�ʂɔ����ĊJ�������P�O�P�n�͌��z��Ԃ悤�ɓ����Ƃ��Ă͍��o�͂́A���Ȃ킿�d�C��H���̃��[�^�[���g���Ă����̂ł��B
�@���̎����͌o�ϐ��d���̐����}���Ƃ��Ă͂��܂�Ȃ������̂ł��傤���A�����܂ł̉����͂ƏȃG�l�𗼗���������@��҂ݏo�����^�]�m�������̂ł��B�J��������R����̎ԗ��̃}�X�R���̃m�b�`�̓J�����̐�����ǂ��܂Ői�߂邩�A�Ƃ����@�\�Ɠ����ɂ��̎��ɗ����d���l�̐���̗v�f�������Ă����̂ł��傤���A�R�m�b�`�A���Ȃ킿����܂łł�����x�܂ʼn���������}�X�R�����ق�̈�u�S�m�b�`�܂Ői�߁A�E����߂ɐi�i������B���̒���ɂȂ����m�b�`���Q�܂ŗ��Ƃ��B����ƃA���s�v�c�I������̉����͓����Ă���̂ɉ��̂��d���l�͂悭�o���Ă��Ȃ����O�D�S���`���x�ɗ}�����Ă���B�i�ʏ�̎�ߊE���^�]�ł͂O�D�W���`���x�j�@��������ēd�͏����}���Ȃ��獂���^�]���������Ă����^�]�m�����X����ꂽ�̂ł��B���܂�ق��ł͌��Ȃ��ł���H�@�O�ɉJ�V�̏��c�}�]�m�����łX�O�O�O�n�̉^�]�m����͂�}�X�R�����S�Ŕ��i�����̂������Q�Ƃ��R�Ƃ��ɖ߂�����s�����肫���肵�Ă����̂��������Ƃ����邪�A����͋�]���������Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă���B
�@���A���炭�����I�^�N�b�ŏI����Ă��܂��܂����B�܁A����Ȃ���ł��Ȃ��E�E�E�B
�O�Q�D�P�O�D�P�T�F����ɏo��
�@�P�S���̓S���L�O���͂R�A�x�Ȃ������Ƃ����̂ɂǂ��̃C�x���g�ɂ��s�����ɃE�`�ʼn߂����Ă��܂����B����͂���ŗL�Ӌ`�Ȉ�����������ǁB�S�t�@���݂̂Ȃ���͂��������̃C�x���g�Ŋy���܂ꂽ�낤�ȁB
�@���āA�����̓o���h���ԁi��y�����ǁj�̏���������ŌW������Ă���Ēm�点�Ă����̂ŁA�s���Ă����B�������A�s�c�V�h���A�c�c�L�y�����ɂāB�R�А���������ǂ�͂�C�x���g�͂P�S���ł��̗������Ă͍̂L�����܂߁A�Ȃ�ɂ�����܂���ł����B�Ȃɂ��ɂ���������ӂ�ӂ���Ƃ������֍s�����Ⴄ���ȁA�Ȃ�Ċ뜜���o���Ȃ���̊O�o���������ǁA�S���̞X�J�ɏI���܂����B�������͂W�O�O�O�n�A�s�c�V�h���͂P�O�|�O�O�O�n�ƑS���ς����̂Ȃ��p�^�[�����������ǁA�L�y�����͂��̃A���~�̂�����F�ɃC�G���[���C���̂V�O�O�O�n���Ƃ���������O���[�h���Ƀu���[���C���̐������������Ă���U�O�O�O�n�i���������̓������A���~�ԑ́j�������B���i����Ă���l�ɂ͂Ȃ�̕ϓN���Ȃ��낤���ǁA���܂ɂ������Ȃ����ɂ͋M�d�ȋ@��ł��B�ŁA�܂��͐����̂u�u�u�e����̉����B���i��芵��Ă��鋞���̂W�O�O�O��������͂����Ɖ����������B��H�d���Ԃł����Ƀ��[�^�[�_���W���Ȃ��ł͂Ȃ����I�@���ꂪ���̏������i�ԓ��ł́j�Ɋ�^���Ă��邩������Ȃ��B��������Ԏ��̋@�B�u���[�L�̖��͊��S�ł�������Ȃ��Ȃ��B�v���ǁI
�@����Ƃ͑S�R�W�Ȃ����ǁA�ˑܑ��̃f�U�C���Ƃ��A�V�O�P�n�����肩��̂��̂��Ȃ�ƂȂ������p���ł��āA�q���̍��𐼕������ʼn߂��������Ƃ��܂��Ă͖��ɐe���݂������Ă��܂��܂����B�Ƃ������ƂŁA�v�X�ɐ����̎ԗ��ɏ���ăz�b�Ƃ��Ă��܂������ł����B�Ȃ�̂�������I
�O�Q�D�P�P�D�P�U�F���V���g���c�b�̒n���S
�@�^�]��͖w�ǂ����l�����ŁA��l��Ԃ݂����B�^�]�͍r���āA�������Ă���~���O�̌����̉����������������ς������B���A���������܂�ɂ��̂����ς��������Ɋ������̂ŁA�����������炻�������v���O�����̂`�s�n�^�]�Ȃ낤���H�@�i�z���g�ɉ���I�j�@�ȑO�����U���m�`�u�h�|�T�Ƃ����}�C�R������̋@�B���I�[�g�}�`�b�N���o�����Ƃ��ɃJ�[�O���t�B�b�N�ƌ����G���̏���ҏW���ł��鏬�я����Y���u���̃v���O�����̂��ƂɂȂ��Ă���^�]�̓R�o���V�V���E�^���E����̂悤�ȃX���[�Y�ȉ^�]�ł͂Ȃ��A�����ƕ��ʂ̉^�]�̂悤���v�ƕ]���Ă����̂���ۓI�������B���V���g���n���S���v���O�����^�]���Ƃ���ƁA����������ȃu���[�L���O������{�ɂ��Ă��܂����̂��낤�B
�@���������V���Ƀh�C�c�ɍs�����Ƃ��̎ʐ^�Ȃ��������̂ł�����Ƃ��Љ�܂��傤
�O�R�D�O�P�D�P�P�F�@�i�q��������ւ̋�s
�@���A�܂�����ǂ��ď����ʐ^�f�ڂ��ĂȂ������ł��ˁA�܂�����ǁI
�@�ŁA�����̘b��͂i�q�����{����������l�^�B�N���̂�����A�Q�O�T�n���T�O�O�O�ԑ��ɏ��܂����B����͂��Ƃ��ƎR����ɂd�Q�R�P�n����������Ă��Ԃꂽ���̂���������ɗ������̂ŁA�����͎�肠�����W�A�Q�{�B�Ȃ��T�O�O�O�ԑ�ŋ敪���Ă��邩�Ƃ����ƁA�Ȃ���E���Y�����������u�u�u�e�ɉ�������Ă��邩��Ȃ�ł��B�R����ł����тꂽ�ԑ́i���ہA�V�[�g�Ȃ��Ȃ�ւ����Ă������A�^�]���Ȃ��������Ɠh���������Ă����j�Ƃu�u�u�e�̃X�e�b�v���X�ȉ������ƃT�E���h���Ȃ�Ƃ��s�ނ荇���Ŗʔ��������B����ɂ��Ă��u�u�u�e�������̗��R���s�v�c�B��������͋��t���ƒ��ʉ^�]���Ă��邽�ߋ��t�g���l����ʉ߂���̂ł����A������ʉ߂���ԗ��͂P���j�b�g�̏�ł����͂Ńg���l���̌��z�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂��ߏ]���̕�������p�Q�O�T�n�͂W�A�ł��U�l�Q�s�Ƃ����ґ�ȕҐ��ł����B���A�R����̗]��Ԃ̊W����l�Ԃ͂��܂萔���Ȃ��A�U�l�Q�s�͑g�߂Ȃ��B���̂��ߔS�������ɗD���u�u�u�e�ɂ��Ă��̏������N���A���悤�Ƃ����Z�i�炵���B����������n�i���[�^�[���H�j�S���Ƃ������邩�˂��E�E�E�B
�@������ɂ�����������P�O�R�n�̂Q�O�T�n���͂ǂ�ǂi���ė~�����B�Ȃɂ��뒷���g���l���������ő��s�������ŁA�P�O�R�n���Ƒ������Ђǂ����āE�E�E�B�n���S�������x�������Ԃ�n���������B�z���g�ɂ��邳����ł��B�m�荇���Ə���Ă��Ă��A�g���l���ɂ͂���Ɖ�b�̓X�g�b�v�ł��B(�L�w�M;)�n�@
�O�R�D�O�P�D�P�P�F���B�o�����|�[�g
�@�܂�����ǁA���Č����Ă��Ă܂��Y�ꂻ��������Ȃ�Ƃ����B�o�����̎��^�ł��ڂ����Ƃ��܂��傤�B
�P�P���O���̏o���̓��V���g���`�k�`�ł������A�㔼�͉��B�̗��B�X�C�X�i�W���l�[���j�`�t�����X�i�x���t�H���g�j�ł����B�ŁA����S���ɏ�ꂽ�͎̂d�����I���Ă̋A�蓹�A�t�����X�̃��[���[�Y�i���{�l�̓~���[���[�Y�Ƃ������A�������ł͊F���[���[�Y�Ƃ����j�����a���������܂ŁB�Ȃ��ړI�n�̃x���t�H���g����ł͂Ȃ����[���[�Y���炩�Ƃ����ƁA�����ɂ��S���������i���L�p���t������j������炵���Ƃ����������O�ɃL���b�`���Ă����̂ŁA�Z�����R���Ԃ����p���Ă����Ɋ���Ă݂悤�ƍl�����̂��B�d���Ŋ�Ȃ��݂ƂȂ����h�C�c�l��Thomas�Ɂi�@�֎Ԃ���Ȃ���I�j�ԂŃ��[���[�Y�܂ŘA��čs���Ă��炢�A�������甎���ق֍s�����Ƃ�����킾�����B���A���������̒��������܂���������Ȃ��B�w�Ŕ����ق̏ꏊ���Ă݂�ƃo�X�ɏ���Ă��炭�s���˂Ȃ�Ȃ��Ƃ̂��ƁB������͂ł������X�[�c�P�[�X�������Ă���̂ŁA�܂��͉w�ɗa���悤���Ǝv�����獡���͋x�݂ŗa����Ȃ��B�o�X�����܂�{�����Ȃ��A�]�X�Ō��ǂ�����߂Ă��܂����B�i���͍s���Ƀt�����X�̃V�������E�h�S�[����`�ň�x�g�����W�b�g�����������Ă��܂������߁A��T�d�ɂȂ炴��Ȃ��ɂ������j
�@�Ƃ������ƂŁA����͋��������S���ɏ�Ԃ��邱�ƂŖ������邱�Ƃɂ����B
��̎ʐ^�͍������a���������܂ł̗�ԂƎԏ������i���̎ԏ��A�a���������Ńr�[���̂�ł����ǁA���[���b�p�����炢���̂��ȁH�j�A���̎ԓ��A�w�Ō��������d�k�A���H�̓����ɂ������ۈ����u�̒n��q�Ƃ��ڂ������́A�w�Ō��������������X�^�C���̎ԗ��̘A�����B�V�����݂����Ȃ��ȁH�Ǝv���Ă��̑O����݂���Ȃ�ƂQ���Ґ��������B�������I
���̎ʐ^�A������A�ؐ��̖��Ȃ̂Ƀ����O���[���̗n�ږ��i��H�t�����X����C���̕ω������Ȃ��̂��̖��ł������O���[�����g����̂��H�A�a���������w�A���[���b�p���Ȃ��A���[���b�p������tram�B������a���������ɂāB���`�A�����A�u���E�̎ԑ�����v�̐��E�ł��Ȃ��B�ŁA�Ō�����[���[�Y�S���������̃p���t�ł��B
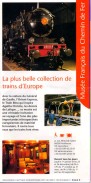
�O�R�D�O�P�D�P�W�F�܂�����������l�^
�@��������͓����̊O����I�v�f�����邽�߁A�������̐���ɂ܂��������������^�]����Ă���܂��B��{����͌��⊙�q�ɍs�����̂Ƃ��A�����q��������ւ������̂Ƃ��B�ŁA�������{�ł��������Ă�����̂Ƃ��āu�����ނ����̍��v�Ƃ����̂�����܂��B����͂��̐́u�V���������[���v�ƌ����Ă������̂ŁA���Ƃ��Ƃ͔����q�����{�܂ł𒆉����A��������A������ݕ������g���Ē��ʂ����Ă������̂��������ꂽ���̂ł��B�ŁA������������ƎO���J���[���P�U�T�C�P�U�X�n���R�{�R�̂U�A�ʼn^�p����Ă���A�������܂ɂ���ɏ���Ƃ��Ă���悤�ȋC���ɂȂ������̂ł����A�P�Q������Ȃ����������J���[�i�Ƃ������Ƃ̓X�J�F�j���P�P�T�n���^�p�����悤�ɂȂ��Ă��܂����B������ĂȂɂ����炭���x���_�E�����Ă��܂����悤�ȋC�����܂��B�@�Q�h�A�A�f�b�L�t�����R�h�A�A�f�b�L�Ȃ��i�~�����A�ď����j�@�A�ȈՃ��N���C�j���O�A�N���X�V�[�g�i�ꕔ�Œ���������킹�j�������O�ƌŒ���������킹�̃Z�~�N���X�V�[�g�@�B��Ԃ��c�s�R�Q���c�s�Q�P�ƃ}�N���o�l���_�C�A�t�������G�A�T�X����R�C���o�l�Ɋi�����@�C���̎Չ��d�l���Ⴄ�݂����A�������傫���悤�Ɏv����B�@�x���̉����͗]��ɂȂ����P�W�R�n�i�Â��Ƃ͂����A���Ă̓��}�ԗ��j���^�p����Ă��邻���Ȃ̂ŁA�ނ����̍��ɂ��Ăق����ȁA�������E�E�E�B
�@���������A�܂��i�I�I�j�������������S���ɘj���Ď~�܂����B���R�͉z�J�̕��Ŗ����R��������B�ǂ�����ꡂ��ޕ��̏o�����̂��߂ɑS���~�߂邩�Ȃ��H�@�����������q�̓T�[�r�X�����ċC�����ł��ߍׂ��ɃV�X�e�����l�������ė~�����ȁB���S������������Ȃ��Ƃ͂Ȃ��ł���H���������䕗�ł���ł��i�q�͂����~�߂��Ⴄ��ˁB�������Ă��鎄�S�͉������Ȃ��^�]���Ă���Ƃ��ł��E�E�E�B���̂ւ܂��܂��e�����̊ێ���̖��c�Ȃ̂��ˁH
�O�R�D�O�X�D�O�W�@�F�x���M�[�A�S���̗�
�@���N�ȏゲ�����������Ⴂ�܂������A���̍ߖłڂ�����Ȃ����ǁA����[��A���ʔłł��悧�`�A���E�̎ԑ�����A�x���M�[�ҁB
�@�܂����u���b�Z���̒n���S����B�@��R�O�����B�Q�`�S�����x�B�ԓ��͑��V�[�g�Ńh�A�͎����Ńn���h���������ƃG�A�ŊJ���^�C�v�B�X�e�����X�ԑ̂Ŏԑ̒[���͖��邢�I�����W�F�B�ǂ����X�e�����X�͎ԑ��X�L���݂̂ō|���������I�����W�ɂ��Ă���悤�Ɏv���܂��B�����͌����@�őO�����Ĕ����܂��B���v���Ԃɂ��]�[���敪�̂悤�ł��B�H���\���ɂ��ܓd�Ԃ��ǂ��̉w�ɂ���Ƃ����\�����ł�̂ł܂��܂��e�B�z�[�������̓����ɖӐl�p�Ƃ��ڂ����������̊���~�����ݒu����Ă��܂��B��ɂ̂�Ƃ����Ⴉ����Ɖ��������B�ԗ�������͂�����ƌ��ɂ������Ǎ������o�l���R�C���Q�{�̂��̂��G�A�T�X�̂��̂Ƃ�����܂����B���Ԃ�S�d���ԂȂ�ł��傤�ˁA�����̓X���[�Y�ł����Ȃ�����x�͍��߂ł����B�i���{�̒n���S���S�R�����������B����̓��V���g���c�b�ł��I�t�F���o�b�n�ł��������B�j
�@����ł͑����ăx���M�[���S�i���Ԃ�j�ҁB�ƌ����Ă�Brussels����Aalst�܂ňړ����������Ȃ̂ŁA�l�^�͏��Ȃ���ł����E�E�E�B
�w�̍s����\���͋�`�݂����ɂ�������\�����Ă܂��B���̍��ɂ������傫���̕\��������A�Q�S��ԂԂ炢���\������Ă��܂��B���Ȃ݂ɂ��܂莞�Ԃ͐��m�ł͂Ȃ��炵���A����������d�Ԃ��T�����炢�x��Ă܂����B�i�܂��ȕ��H�j�@����Ă����d���͂P�l�Q�s�̂R���Ґ��B�Ō�����l�ԂȂ�ł����A�Ȃ����y�^�̃p���^�͐擪�Ԃɂ��Ă܂����B�ԑ̂ƃv���b�g�t�H�[���Ƃ̍��፷�͂����̂悤�ɂ��Ȃ�傫���X�e�b�v�R�i������܂����B�q���h�A�͉�]����|�[���ɃA�[�����t�����v���O�h�A�ŁA����͒n���S���������������ȁB�q���h�A�͂����̂悤���ԏ����L�[�Ń��b�N���������Đg�߂ȃh�A����{�^�������ŊJ���܂����B����͕��ƍ����݂����Ȋ����ŁA�g���[���[�̓~���f�����A�d���Ԃ̓A���X�g�[�����ł����B�i�ȑO���Ċ������̂͑�Ԃ͂ق�ƂɊe���͂����肵�Ă���Ƃ������ƂŁA�t�����X�̓A���X�g�[��������A�h�C�c�̓~���f���E�h�C�c������ł����B���{�́H�ŋ߂̓{���X�^���X�̐蒣��H�݂����Ȃ��Ⴟ�Ȃ��̂��嗬�ɂȂ��Ă��܂��܂����ˁB�j�@���������A��Ԃ̑���́A�Ƃ����ƒn���S�Ƃ͐����ŁA�����͐̂̋q�ԗ�ԂȂ݂ɂƂ낭�ċ����܂��B���������l�ŁA�������̉����q�Ԃ��̂��̂̃V���[�Ƃ����������܂��B�����N���[�Y���x�͂���Ȃ�ɍ����悤�ł��B���[���̃W���C���g�ʉ߉��͂قƂ�ǂ��������A�����O���[���ɂȂ��Ă���悤�ł��ˁB
�@�͂��A����ł̓x���M�[�����A���̕ӂŎ��炵�܂��B
�O�R�D�P�O�D�P�Q�@�F���Ђ��Љ�
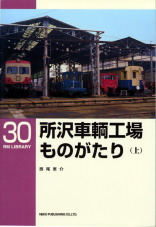
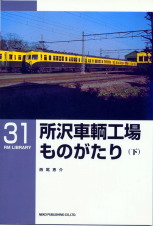 �@����������{�������Ă��邤�邵�A���Ă��܂����B����ł��A����`��I�@����������q�H��ƌ����ΐ����i���C�I���Y����Ȃ���j�t�@���Ȃ�N�ł��m���Ă�A�֓��̑�莄�S�ł͗B�ꎩ�ЂŎ��q���Y���s���Ă������j�[�N�Ȏ��q�H��ł��B
�@����������{�������Ă��邤�邵�A���Ă��܂����B����ł��A����`��I�@����������q�H��ƌ����ΐ����i���C�I���Y����Ȃ���j�t�@���Ȃ�N�ł��m���Ă�A�֓��̑�莄�S�ł͗B�ꎩ�ЂŎ��q���Y���s���Ă������j�[�N�Ȏ��q�H��ł��B�@����̗���ƂƂ��ɂ��̖������I�����ƕ����Ă��܂������A�܂�������ȕ��Ɏ����Ƃ��Ă܂Ƃ߂��{���łĂ����Ƃ́E�E�E�B(�d�A)�A
�@�������S��������ɂ͐����̃J���[�͂��łɃt�@���̊ԂŐԓd�ƒʏ̂���邭�����[�Y�ƃx�[�W���̃c�[�g���ɂȂ��Ă��܂������A���̖{�ł͂��̂����Ƃ����ƑO����i�H�ꂪ�ł���O�A����㓖���j��������Ă��āA�y�[�W���͏��Ȃ��ł����A�M�d�Ȏʐ^���܂܂�Ă��āA�������Ƃ�����B
�@���ƈꏏ�Ɂu�Ȃ��N����S�����́v�i�������͌�ʈ��S�̎d���̎Q�l�ɂ��Ȃ�j�Ƃ����{���܂������A�ݕ��Ƃ��q�ԗ�Ԃ̈�Ԍ��ɂȂ���Ă����ԏ��̏���Ă�����q�A�ɋ}�Ԃƌ����āu�t�v�̋L�������Ă��܂����A���ꂪ���Ƃ��ƃu���[�L�������邽�߂ɂȂ���Ă������q�Łu�t�v�̓u���[�L�̃u�̑��_����������̂��Ƃ������Ƃ����߂Ēm��܂����B
�O�R�D�P�Q�D�O�R�F�@�v�X�̐������̗�
�@����A�v�X�ɂ������Ȉ�@�֍s���A���̍ۂɂ����̂Ƃ���s�c��]�ː����p�������Ďg��Ȃ��Ȃ��ė��Ă��������r�ܐ��ɏ�����B
�@���Ȉ�@�͒r�܂��炽�����R�߂̍]�Óc�Ƃ����w�̋߂��ɂ���A�����܂ł̏�Ԃ��Ǝ������]�Óc�ɏZ��ł������Ƃ��܂�{�݂����q���ς��������Ȃ��悤�ȋC�����Ă����B�i�e�₾�Ƃ��܂�V�������q�̏o�Ԃ��Ȃ��悤�����j
�@�ŁA����͂܂��������ʂȉ����ŋA�邱�Ƃɂ����B���Œr�܂ɖ߂�̂ł͂Ȃ��A����ŏH�Â���ʋŎg������������o�R���ċA��A�Ȃ�Ă̂͂ǂ����H�@�ĂȂ��ƂŁA�]�Óc����܂��͉���e��ɏ��B
�@�����͖̂L�����s���e��B���q�͂�͂肢�܂�Ê��̂P�O�P�n�B�]�Óc���o�Ăт�����B�����܂ł͂قƂ�Ǖς��Ȃ������i�F�������ƕς��B�����Ȃ��n��̒ʉ߉w����������͍��ː���̉w�ƂȂ�A�ߑ�I�Ȗʂ����ƂȂ��đS�����̒m���Ă���w�̖ʉe�͂Ȃ��B����ɏ���Ă݂Đ����B���̂܂ܗ��n�w�ցB�����ŖL�����͕���ɂȂ邽�ߖ{���ɏ�芷����B
�@���x�͏��}������炵���B������I�悤�₭�ŐV�̂Q�O�O�O�O�n�ɑ����B�������̃����n���h���R���g���[���[�ŁA�悤�₭���S�̍ŐV�����ɒǂ������Ǝv������q������������o�Ă����B����o���Ɖ������R�D�OKm/h/s�̌��\�l�Ɉ�킸���������ǂ��B�ŁA�������̂����x�B�����͓ݑ��A�Ƃ�������ς����������A���̂܂ɂ��r�ܐ����������グ��ꂽ�悤���B���C�Ȃ��P�O�O�����^���܂ł͏o���悤�ɂȂ��Ă����B�ւ����E�E�E�B�i����ł���������Ă��鋞�����̉����x�R�D�R�A�ō����P�P�T�����^���Ɣ�ׂĂ͉��z�����E�E�E�j�����A�Q�O�O�O�O�n�ŏ����Ⴄ�̂����s���ɗ��J���̋q���h�A��������p�^�p�^�Ƃ������B������Ă��ɂ����̂T�T�P�C�V�O�P�C�W�O�P�C�S�P�P�n�����肪�g���Ă������Ǒϋv���̊W�Œ��������Ȃ������A���~�E�n�j�J���h�A�i�A���~�̖I�̑���̍\�������ɓ����Ă���y�ʃh�A�j�Ƃ܂����������������B���̌�̎��q�݂͂ȂP�O�P�n�ȗ��̃X�e�����X�E�v���X�E�h�A�ł���Ȍy�����͂��Ȃ��Ȃ��Ă����̂ɁE�E�E�E�B
�@�ΐ_������ō��x�͋}�s�ɏ�芷����B�����̂͂Q�O�O�O�n�����A�Ǝv���Ďԓ��ɓ����Ă���v���[�g���݂���X�O�O�O�n�������B�J�b�R�͓����ł��Q�O�O�O�͊E���`���b�p�̉����A�X�O�O�O�͔p�ԂɂȂ����P�O�P�n�̔p�i���p�ɂ���R����B�ǂ�Ȃ��ȁH����ɂ��Ă��ԗ֓��ʂ̍r��ɂ��Ǝv���邲�낲�뉹���Ђǂ��ȁB������u�u�u�e�C���o�[�^�[�{�����݂����ȕt���Вx�ꍞ�߁i�u���[�L�������グ�邽�߂Ƀ��[�^�[�Ȃ��̎Ԃ͂ł��邾���u���[�L�������Ȃ��悤�A�G�A�̏[�U��x�点��j���Ȃ����߂ɃN�n�ł��t���Ƀu���[�L���g���������ȁH�@�ł��X�O�O�O�n�Ƃ��čX�V���ꂽ�ۂɃt���b�g�h�~���u���t����ꂽ���ď����Ă��������ǁH�H�@�����̏�œd���v�߂�B��H�@�₽��j�̓����������B�P�O�P�n�Ɗ�{�I�ɓ����͂��Ȃ̂ɁE�E�E�E�B���������ĂX�O�O�O�ł͂P�O�P�n�ł̓u���[�J�[�Ő�ւ��邱�Ƃ��ł����������ݒ�i���Ԃ�J����������탂�[�^�[�𑁂������j���펞�g�p�ɂȂ��Ă���̂����B�ŁA���낲��Ƃ��邳���������ǁA���x�͂�͂�̂��͍����āA�P�O�O�����^���͏o���悤�ɂȂ��Ă����B���₠�A�i���i���B����͂P�O�P�n�ȑO�̎��q�����݂��Ă����炠�蓾�Ȃ��������낤�ȁB
�@�����ň���s�B�~��悤�Ǝv���Ă����H�Â͋}�s�ł͎~�܂�Ȃ��̂������B�ŁA����܂ōs���Ă��܂����B���āA�ǂ����邩�H
�@�e��ň�߂��ďH�Â��畐������@�A�r�ܐ��Œr�܂֖߂�@�B�V�h���Ő����V�h��
�@���������B�̃I�v�V������I�B�����̂͂Q�O�O�O�n�̋}�s�B�V�h�������������ꂽ�̂��ȁH�Ɗ��҂���������A�c�O�A��������������͂���Ă���悤�����A�ō����͂X�O�����^���̂悤���B���܂�ς��Ƃ��Ȃ�����Ő����V�h�ɒ����Ă��܂����B
�@���ꂶ�Ⴀ�A��̋������Ō������ł����邩�A�Ǝv���Ă������A�Ȃ����āA�������ł͒��ԎԂ̍��ȂŖ���A�������ʂ̏�q�ɐ��艺�����Ă��܂������}�P���ł����B
�O�S�D�O�P�D�O�P�F�W���l�[���̃z�e���ɂ�
�@������ƒx��܂������P�Q���n�߂ɃX�C�X�̓W���l�[���֍s�������̋L�^�����Љ�܂��傤�B����͓S�H�̗��p�̗\�肪�Ȃ������̂œS���̕s�����\�z���ꂽ�̂ł����A���B�o���̒ʗ�Ŗ�X�����Ƀz�e���ɓ������A�X�[�c�P�[�X����ו����o���ĂƂ肠���������ł���̐��𐮂��A�ق��ƈꑧ���ă\�t�@�ɗ��������ƁA��H�����S���̒ʉ߉��̂悤�ȉ��I�@����Ăđ��̃J�[�e�����J����ƈÈł̂Ȃ��A��s��Ԃ̑��̖�����̗ʂ�߂��Ă����B������I���̃p�[�L���O�G���A�̂����ׂ�̈�i�Ⴂ�Ƃ���͐��H�������I
�@�����A�ߌォ��̉�c�ɔ����A�����Ŏ����Â�������ʉ߂����ԉ��Ɏ��܂��A���������ʂɐ������܂����B
�ƁA�����ւȂɂ��I�����W�F�̖h����ƕ����܂Ƃ����l�������W���B�Ȃɂ��n�܂邩�Ǝv���A�N���[���̂����f�B�[�[���̍�ƎԂ��o��B���H�e�̐M���P�[�u���p�̑��a�����n�߂��B
��Ƃ̊Ԃɂ���Ԃ͒ʂ�B�����쐬�̂������A�B�e���E�E�E�B
�ߌ�̓������ŌŒ葋�̔��˂��������Ȃ��Ȃ��Ă����B��c�̂��߂̊O�o�̎��ɏ������߂ɏo�ăz�e���̃p�[�L���O�ŗ�Ԃ�҂��Ă݂邱�Ƃɂ����B
����ɂ��Ă���ԏ�E�̂��̈ȊO�قƂ�ǂ��d�k�{�o�b�̗�ԂȂ�ł����A�ǂ����Ă����o�I�ɑ��e��Ȃ��̂����ł�����ł��d�k�̈ʒu��ς��Ȃ��ł��̂܂܉^�s���Ă��邱�ƁB�܂���łd�k���������Ă����Ƃ���ƁA���̗�Ԃ͉���ł͂d�k���o�b�𐄐i�^�]���Ă����ł��B���̂܂ܒ��N�^�s���Ă��������v�Ȃ낤���ǁA�Ȃ��Ȃ��E�E�E�E�B
�O�S�D�O�P�D�P�O�F�@�_�ˁA�L�n�ւ̏o��
�@�d���n�ߑ��X�A��c�Ő_�˂���k�ɏ�����Ƃ���ɂ���L�n�i����j�֍s���܂����B���R�S�����g���܂����̂ŁA�����s���A��̃��|�[�g�����Ă��������Ǝv���܂��B
���H
�@�V���l���V�_�ˁF�̂��݁i�V�O�O�n�j
���߂Ă̂��݂ɏ��܂����B�V���l�ő҂��Ă���Ƃ��Ɋ֓��ł͐����Ȃ��i�Ǝv���j�T�O�O�n�̂��݂����������̂ŃX�i�b�v�I

�Ȃ��i�D�͂����̂����A�ԑ̒f�ʂ��������Ďԓ��ł͈����������肻���B���ƁA���̂悤�ɂ����ו��̑����l�ɂ͌����Ȃ������B�V�����ł̓p���_�O���t�̐������������̑傫�ȃt�@�N�^�[�ƂȂ邽�߁A�J�Ǝ��̂O�n�ł͂P�U���łW�������������̂��A���܂ł͍����n�����ݒu���āA�n�㑤�̂��d�������ύX���邱�Ƃɂ���ĂQ�����Ɍ����A���������艹��ł���ȎՕ����t���Ă���B���ׂ̗�͂V�O�O�n�̎ԑ̒[���ɂ��Ă���_���p�[�B�̂�����}�d�ԓ��ɂ͎ԑ̓��m�Ƀ_���p�[�����ėh�����R���g���[�����Ă������A�ŋ߂̐V�����ł͂���ȃ^�C�v�Ȃ�ł��ˁB
�V�_�˂ɓ����B�V�_�˂���Z�b�R���т��g���l������B����͐_�ˎs�̒n���S�̎��q�����̂܂܉^�s���Ă������A�V�_�˂����̘Z�b�R���镔���̓����}���ŁA�����������^�]�̂悤���B�i�d���v�����Ă���ƃI���I�t���Ȃ��A�قƂ�Lj��l���w���Ă���A���z�ɉ����Ď�{�|���Ă����B����Ǝ������Ɗm�M�����͉̂^�]�䒆���̔����{�^���Q������������B��������]�ː��̎��q�ɂ����Ă��āA�o�����ɉ^�]�m���E�����ꂼ��̃{�^���𗼎�̐e�w�ʼn����Ă����B�j
���q�͒��ʂ����H���͕ʂŁA�k�_�}�s�Ƃ������O�����Ă����B

���`�ɂ��Ȃ��Ă����̂ŁA�����͂��̂ւ�ŁB�����͂܂���̒��q�̂����Ƃ��ɁB
�O�S�D�O�Q�D�P�O�F�@�_�ˁA�L�n�ւ̏o���i���̂Q�j
�@�悤�₭��A���ɂ��ǂ��Ȃ��Ă����Ǝv������A������̃E�B�[�N�|�C���g�ł��鍘������Ȃ��Ă����B�����ł��Ȃ��B
���āA��L�̑����ł��B
�@�k�_�}�s�ŒJ��ɂ��Ƃ��悢�悱������Z�b�̐F�������Z���Ȃ��Ă��܂����B�_�˓d�S�͂���܂���A����Ȃ��ėL�n���B
����Ă����̂́i���Ԃ�j�A���~�ԑ̂����ǃI�����W�F�̕��������Ȃ葽���R�O�O�O�n�B�^�]����`���Ă݂�ƃ����n���h���E�}�X�R���ŁA�Ȃ��Ȃ��ߑ�I�B��H�@�����n���h������Ȃ��I�E��͂�������N���V�b�N�ȃu���[�L�ق��I�@���Ⴀ����̃n���h���̂m���O�ƌ��́H�@�����ł悤�₭�������R�x�H���ł��邱�Ƃ��v���o�����B���������A�}�����������A�Ƃ���Ɣ[���B���������������^�C�v�̃n���h���̗}���u���[�L�͏��߂Č����B�L�n���ł���ɗL�n����֍s���͂���w�̎x���ɏ�芷���L�n����A�I�_�ł��B�����œ�����c�ɏo�Ȃ���r����Əo��A�w�O�̐H���Œ��H�B����ς萼�֗����琼�̂��ǂ�ł���I�Ƃ������Ƃł���B����ԂƂ������̂����Ղ肩���������ǂ�ł��B
�@�����ł͈ȑO�A�e���r�̃N�C�Y�ԑg�������ŕ��������Ƃ̂��鎖���������ōĊm�F���邱�Ƃ��ł����B�r����͂����Ȃ������炫�˂��ǂ�𗊂̂����A���������ɗ��������܂͒�����Ɍ������āu���ʂ��I�v�ƌ������B����H�Ǝv���A�����Ȃ������������ƈĂ̒�A�����Ȃ����ɂ́u���ʂ��v�͂Ȃ��B�ŁA�łĂ����̂͂��g���̂��˂��ǂ����B�����A�ǂ����̒n��ł͂��˂��ǂ�̂��Ƃ����ʂ��ƌ����ƌ����Ă������A�܂��ɂ����̂��Ƃ������̂��B
�@�����Ƃ����ԂɂP�����̉�c�͏I���i�z���g����H�I�j�A�r�ɂ��B�Ƃ肠�����o������Z���鐳�K�̎������m�F������ŁA���X�����̊��n��S���̃~�j�c�A�[�ɏo��B�Ƃ肠�����A�܂������������[�g�ŋA�炸�A���������ėL�n����|�L�n���|�V�J�n�|�����|�O�{�|�V�_�˂ŋA�邱�Ƃɂ����B
�O�S�D�O�Q�D�P�R�F�@�_�ˁA�L�n�ւ̏o���i���̂R�j�@
�͂��͂��A����ł͈��������ă~�j�c�A�[�̑��҂܂���܂��傤�B
�L�n����ЂƂ܂��_�˓d�S�̖{���w�A�L�n���������B����Ă����̂͂P�O�O�O�n�B�ђʎ��̉^�]���͂����̂悤�ȃR���p�N�g�Ȃ��̂ŁA���������R�O�O�O�n�̑S���A�c�^�R���g���[���[�Ƃ͐������͋C���Ⴄ�B�����ė�����悤�L�n���w�̕��i�B
�ŁA�V�J�n�������ׂ��_�S�L�n���ł���Ă����̂͗L�n������Ɠ����P�O�O�O�n�B�w���o���Ƃ���ɂ͕s�v�c�ȃ��[�o�[�`��̂��̂��������B�r���A���������̂Ɠ����R�O�O�O�n�Ƃ�����Ⴄ�B
�ʂ̐��ƕ���ƂȂ�闖��ɂāB�P�O�O�O�n�ƂT�O�O�O�n���ȂށB������z��}�������ʼn����Ă���Ƃ���B�}�X�R���̈ʒu�ƃ}�C�i�X���w���Ă���d���v�i�u���[�L�ىE�j�ɒ��ځB�����ĐV�J�n�ɓ����B�����Ƃ����ɉ߂��Ă����̂ŗ����H�����ǂ�B������Ȃ��u�ڂ��������ǂ�v�Ƃ����̂������Ă݂�B�g�b�s���O���ڂ������Ƃ������̂̂悤���B����ɂႭ�Ƌ����������ϕt�������̂Ƃ��������B���炵���ݖ����͔��߂ŁA�������������B�i�ڂ������͂��̂��Ƃł܂����ڂɂ�����@��E�E�E�j
��������R�z�d�S�ɏ��B�q���̍��A�Ȃ����R�z�d�S�ɂ�������Ă��B�������S�Ȃ̂ɕW���O�Ŏ��q���A���~�J�[����������ƂȂ��Ȃ��ӗ~�I�B����ȂȂ��ł��̂R�O�O�O�n�͕i�̂���f�U�C���ł��C�ɓ���ł������A���߂Ď��ۂɂ��ڂɂ�����R�O�O�O�n�͈Ⴄ�h�F�ɂȂ��Ă���܂����B�����Ă��ׂ̃z�[���͍�}�������B��}���}���[���̎ԑ̂ɔ����܂ǂ̃t�`�ǂ蓙���q���Ȃ���ɃG���K���g�Ȋ����Ɏv�������̂ł����B�ŁA������̂͂T�O�O�O�n�̓��}�B�^�]�m����̌��f��h�����߂ɃX�g���{�������Ă����̂łT�O�O�O�n�̎ʐ^�A���Ȃ�Ԃꂽ�B
�T�O�O�O�n�̉^�]�����B���\�͈����Ȃ����������A�Ȃ����W�O�L�����炢�����o���Ȃ��B�r���i�q�ƘA�����Ă��鐂���ŏ�芷���ĎO�{�֖߂낤���Ǝv���Ă����̂�����ɂ��������R�z�ɏ�邱�Ƃɂ����B������ƕ�����Ȃ��āE�E�E�B
�O�S�D�O�Q�D�P�T�F�@�_�ˁA�L�n�ւ̏o���i���̂S�j�@
�����w�Ŏ��̓d�Ԃ�҂ԉw�̗����H�����ǂ�`���B�ƁA�����A��p�Ȃ�Ă̂��������̂ŁA�v�킸�����Ă��܂��܂����B�����̒��H�ɂȂ����̂͌����܂ł�����܂���B
�҂��Ƃ����A����Ă������ʓ��}�͂܂����T�O�O�O�n�B���āA�ǂ�Ȃ���ł��傤�Ɖ^�]��������璭�߂Ă�����A���̋�Ԃ͔�r�I�����炵���ǂ��A�Ȑ����ɂ����߂��y�[�X�͏オ��A�P�P�Okm/h�܂ł͏o���Ă����B��͂肱���łȂ��ƃC���[�W�ɍ��킢�B�����������̂T�O�O�O�n�Ŗʔ��������͓̂d�q�z�[���̃X�C�b�`�B�f�X�N��̃p�l��������O�ɂ���^�b�`�p�l�������̃X�C�b�`�ɂȂ��Ă���A�w��ł�����ƃ^�b�`����Ɓu�t�@�[���v�Ƃ�����̓d�q�����Ȃ�悤�ɂȂ��Ă��܂����B
�@�Ƃ������ƂŁA���̂i�q�Ƃ̘A���w�A�����ʼn��Ԃ��A�V�����Ƃ����̂ŎO�{�֖߂邱�Ƃɂ���B�ŁA�����ň���s���������B�A��͐V�����̐V�_�˂���̐ؕ����������̂ŁA�_�ˎs���͍s���������R�������̂����A�����̓G���A�O�ɂȂ��Ă��܂��Ă������߁A�i�q�̐����Ήw�ɓ���ۂɐؕ��킳��Ă��܂����A�܂��A�����Ȏ��s�ł����E�E�E�B
���āA�V�����������A�Q�Q�R�n�Ƃ������q�������B�^�]�m�͂قƂ�ǔ����̏��V�̕����������A�ǂ�ȑ��肩�Ǝv���A�w���ď̂����炩�ɐ����̂����ԈȊO�͏o�����ςȂ��̂P�Q�Okm/h�^�]�I���̋�����Ԃւ̂i�q�̈ӋC���݂��Ђ��Ђ��Ɗ������鑖��ł����B
���āA�O�{���琼���ւ͂i�q���Ȃ����Ă��Ȃ��̂Œn���S�ŁB���̒n���S���L�n���������Ƃ��̖k�_�}�s�֒��ʂ��Ă���킯�ŁA�Ȃ����肵�Ă����Ȃ��A�Ƃ������S�������܂����B�V�����͋A����V�O�O�n�̂��݂�������ł����A�z�[���ő҂��Ă���Ԃɒ��������̂������B�����c�Ɖ^�]����͑ނ��Ă����Ȃ����������H����O�O�O�n����ˁH�@�₽��Z���Ґ��ŐF���O���[�݂����ȓh�F�B�ԓ�������Ƃ܂�ŕۈ牀�̂悤�ȗl���B�ȂႱ��H�Ƃ��������ł����B
�@�Ƃ���ŁA�V�_�ˉw�ł̃n�v�j���O�I�@���߂͂Ȃ�ƃt�W�e���r�ŕ��f����Ă��܂��܂����B�w�œy�Y�F���Ă�����A�V�J�n�̂��ǂɂ������u�ڂ������v�Ȃ�H�ו������낢��Ɣ����Ă���B�ӂ���A�����̉����A�ǂꂩ�����ċA�邩�ƑI��ł�����˔@���ꂽ���P���I�����Ē��c���̏��H��c���̉�̂悤�Ȑl������B�Ȃɂ�璷�c�̐k�Ќ�̒��������ɂ��̂ڂ��������g���Ă��ꂱ��Ə��i�����Ă���A���傤�ǔ���o���̍Œ��������悤���B�ŁA��������o���ł����T�����[�}������������H���Ă݂ċC�ɓ����Ĕ����ċA��Ƃ����X�g�[���[�̃��f���Ɏ������̏�Ŕ��F����Ă��܂��܂����B�䎌�ȂȂɂ��ł����킹�Ȃ�����S�����Ɖ�̃A�h���u�̉��V�I��T�[�r�X�Ŏ��ۂɔ����V�[���܂ł���Ă����܂����B�i�i�h�a�`�q�`����j�@�ŁA���̃V�[���͏I���A������Ɨ���ċx��ł�����`�c�炵���l�����ł��āA���������������i�̑���ƋL�O�i�i�t�W�e���r�̃|�X�g�C�b�g�Z�b�g�j������܂����B���T�̃I���E�G�A�͂�������^�悵�Ȃ��猩�Ă܂����B���ۂɎg��ꂽ�V�[���͂����͂��ł������A�A�h���u�ł���ׂ����䎌�������t���ŗ��ꂽ�̂ɂ͂�����Ɗ����A���ȁH
�E��ɂ͉�������Ȃ�������ł����A�I���E�G�A�����ɓ�l����u����ȂƂ��ʼn�����Ă�́H�v�ƌ����A����Ɍ����l����u���܂�����v�ƌ����܂����B�ӂ���A���ƌ����Ă����ł��ˁB
�O�S�D�O�Q�D
�@�J�[�I�[�f�B�I�̏C�����ł����̂ň�����聕���t���̂��߂ɔ����q����������̈䉬�ƌ����Ƃ���ɍs�����B��Ƃ��Ă���ԁA�����V�h���ŐV�h�܂Ŕ������ɍs�����B
�@�䉬���琼���V�h�܂ł͂Q�O�O�O�O�n�������B����Ŕ��܂����͔̂@���ɂ��O���������̃R���g���[���[�������x�������Ƃ���炵���A�����ƃu���[�L�n���h���̒u���ꂪ�m�ۂ���Ă��邱�Ƃ��ȁA�E�ʐ^����������B�܂��Ⴛ���ȉ^�]�m���̓}�X�R���̔����ȑ��삪���ɂ����̂��A����ő��삷��n���h���Ɏ��X�E���Y���ăm�b�`�̈ړ������Ă����B����̖��Ȃ̂��A�n�[�h�ʂ̖��Ȃ̂��H
�@���H�̐����V�h����䉬�͂U�O�O�O�n�̋}�s�ƂQ�O�O�O�n�̊e�₾�����B�n��łU�O�O�O�n�ɏ�Ԃ��ĉ^�]���i�߂�̂͏��߂Ă��������A�ǂ��������ɂ͎��炾���Q�O�O�O�O�n�̂悤�ȃn���h�����̂Ȃ���̂Q�R���g���[���̂���̕�����������Ƃ���B������̊���̖��Ƃ͎v���̂ł����B
�O�S�D�O�R�D�O�V �x���M�[�o����
�@��T�Ԃ̃x���M�[�o������߂�܂����B�c�O�Ȃ��獡��͂��̃y�[�W�̃l�^�͂���܂���ł����B���̂Ԃ����Ƃ�����Leuven�Ƃ����Â������݂̕��͋C���A�b�v���܂��̂ŁA��������y����ł��������܂��B
�O�S�D�O�U�D�Q�U�@�X�C�X�A�x���M�[�o����
�@���āA�܂����Ă��o���ł����B����͂���قǖڐV�������̂͂���܂��A��u�S�v�ɐG��邱�Ƃ��ł��܂����B
�i�P�j�W���l�[���ҁF�O�l�z�e�����璭�߂�S���Ȃ�ł����E�E�E�B
�i���j�O��̃W���l�[���̎��ƈႤ�z�e���������̂ŁA����p�x������Ėʔ��������B�E�Ɏʂ��Ă���̂��O�܂����z�e���Ȃ�ł��B�@�i���j���͍��̎ʐ^�̐��H�͂����ƌ������܂ŒH��Ƃ����Ȃ��Ă�����ł��B�@�i�E�j�ŁA���̂�������݂�ƁA���炱��ȐV��ʃV�X�e���݂����Ȃ������Ă܂����B�m��Ȃ������I
�i�Q�j�u���b�Z���ҁF�ق�̂킸���ł����A�u���b�Z����`���璆���w�܂ł̈ړ��ɓS�����g���܂����B�o���҂͑�̃^�N�V�[�ōs���Ă��܂��݂����ł����E�E�B
�i���j��`�w�͒n���B���q�͂���ȐF�łȂ��Ȃ����ꂢ�B�z�[���Ǝ��q�̍����̍��͗�ɂ���đ傫���A�d���ו��̃��^�V�ɂ͏�~�Ԃ���ς������B��H���͈ꎞ���̍��S���g���Ă����悤�ȃ��j�b�g���Ǝԑ̊O��������t����^�C�v���H�@�i���j���̎ԓ��B�V���v���Ȍ��������킹�V�[�g�B�V�[�g�s�b�`���ׂ�ڂ��ɑ傫���Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A�i�q�P�P�P�C�P�P�R�C�P�P�T�n������̌��������킹�Ƃ͊r�ׂ��̂ɂȂ�Ȃ��قǍL���B�@�i�E�j���̓����B�㑤�P�^�R�̉E�������X���C�h���邾���B�����Ƃ��͐h�������ȁB���̉��ɗ��ĂĂ���̂���Ԍ��B�q���݂ɑ傫���B
�i���j�A�����A�������͉��B�̎��q�炵���A���������R�~���[�^�[�I�H���̎��q�ł��傫�ȎԒ[�o�b�t�@�[���撣���Ă���B�d�����I�@�i���j����ʂ����H���𑖂�̂͂���Ȏ��q�����B�@�i�E�j�ԑ�����B���ԏꂩ�H�}���[���ɔ��т̂�����ƌÂ��������G���K���g�ȋq�Ԃ������e���Ă����B
�i���j�@�ԑ�����B�@�ɂ��B�ݕ��p�̋@�֎Ԃ݂͂ȌÂ����B�A�����J������̂��̂ɂ悭���Ă���B�@�i���j�ԑ�����B������ݕ��p�Ǝv����@�֎ԁB�@�i�E�j�@�����炤���Ă�����ăX�}�[�g�ȗ��q�p�@�֎ԁB�t�����X���S���ۂ��H
�i���j�ԑ�����B�����������h�Ȍ����i����H�j���₦�ԂȂ������B�@�i���j�u���b�Z�������w�B�������n���w�����A���̍L�����s�v�c�ɕ����яオ���Ă���B�f�ʂ��Ă���H�@�i�E�j��������l�B�����������č����ۂ��Ȃ��Ă��邩��悯���R���g���X�g���͂����肵�Ă��܂��̂��E�E�E�B
�@���`�A���������u���b�Z���ɂ������̂�����s�����������i�������̐��J�������ԓ��}�j�ɂł���肽�������Ȃ��B�܂�����B
�O�S�D�P�O�D�O�T
�@�o���L�^���e�I�@�I�[�X�g���A�̃O���[�c�Ƃ����X�̓g�����V���ł����B���������̕��i�������ɓ���܂��B
����̓I�[�X�g���A�̓S�������ق̂��b�̗\��I�I
�O�S�D�P�O�D�O�W
�@�͂��A���ʂ�A�S�������ق̂��b�B���̓I�[�X�g���A���ēS�������ق��₽�炽�������ł��B�ŁA����K�ꂽGraz�Ƃ����X�̃z�e���̃p���t���b�g������ƁA�Q�R���������ق����������Ȃ��Ƃ���ɂ��肻���B
�@�Ƃ������Ƃŋ�`�փ`�P�b�g���ɍs�����łɃ^�N�V�[�ōs���Ă݂邩�ȁH�ƃ^�N�V�[�̉^�����ɕ����ƁA�s���Ă��ꂻ���ȕ��͋C�B���Ⴀ�o���A�Ƒ���o���Ɖ^�����A�h�C�c�ꂵ���m�f�B�܂������Ȃ��A�ƃp���t���b�g�����Ȃ���s�������Ƃ�����w�����邪�A�m��Ȃ��炵���B���낤�낵��������A�P�[�^�C�ŒN���ɕ����ĂƂ肠�����ǂ����������đ���o�����B
�@�������Ƃ���͏����ȉw�B��H�@�����ق���Ȃ������A�Ɓu�m�����Y�B�A���A�o���z�t�I�v�ƕ����Ă݂����A�������������Ƃ����B
�@�ǂ����ɂ���A���̉^�����A����ȏ�̍s����͂Ȃ����A�Ƃ肠�����w������A�ň��ł��S���łǂ����֍s�����A�ƍ~�肽�B�ŁA�ҍ����̂悤�ȕ������Ă����ƁA����Ȋ����̂Ƃ���ɗ��܂����B
�����͉w�̉^�s�Ǘ����Ƃ������A�|�C���g��M�����ւ��镔����������ł��ˁB�w���Ǝԏ������ׂ��Ă܂����B
�@�����قɗ������Ƃ�������ƁA���܃^�N�V�[�ŗ�����A���Ă���ƌ���ꂽ�B���������̏����������قł悩�����炠��Ƃ̂��ƁB���������������Ԃ����邩��A���ꂪ�s�����献�n�����猩�Ă��Ă�����B���ƁA���H�̔��Α��ɂ͋@�֎Ԃ��u���Ă���Ƃ����B���`�ށA����͗\�z�Ƃ͏��X�Ⴄ�Ȃ���ʔ������ƂɂȂ��Ă����B
�@���֓���Ƃ����Ȃ�s�C���Ȃ��}���B�w���̃R�X�`���[�����܂Ƃ����}�l�L������B���`�A���킩�����I�@����ɒ��ɓ���ƌÂ����R���N�V�����A�����Ăr�k�̃{�C���[��������������̂̓W���B
�@����Ƀ|�C���g��ւ����o�[�A�����ȉw�̃x���`�A�ؐ��B���̒����̂����V�����m�͂Ȃɂ��Ǝv������A�Ȃ�ƃL�b�v�i�������d���j�̓��t�ō��@�ł����B�Ȃ�Ƒ傰���ȁI
�@�Ƃ������ƂŁA���̑����͂܂�����B