・10.06 BUZZ FEITEN BAND featuring BRANDON FIELDS cotton club 東京
メロディアスだけどホット! たぶん一番好きなサックスプレイヤー
Brandon Fieldsのページ
祝! 2010年6月 Buzz Feiten & Brandon Fields 来日。
・10.06 BUZZ FEITEN BAND featuring BRANDON FIELDS cotton club 東京
ヤマケンの一番好きなジャンルといえばやはりフュージョン!楽器はギター!ですが、フュージョンと言えばどうしてもサックスは外せない! で、そんな中でもヤマケンが(たぶん(^_^;))一番好きなのはLA系のBrandon Fields。 出会いは?というと自分の認識の上ではRippingtons featuring Russ Freeman のアルバム、 「キリマンジャロ」。もしかしたらそれよりももっともっと前から知らずに聴いていたかもしれないけど、(その可能性は大きい。何しろスタジオワークの多い人なので・・・。)認識の上ではとりあえずこれです。
「愚者楽」の話題の中心であるギタリスト、和田アキラ氏も以前のクリニック(確か新宿WINS(場外馬券売場)裏の練習スタジオでのこと)で好きなプレイヤーの一人に挙げていて、偶然ながら好みが一致したことを嬉しく感じたものでした。(それってちょっとミーハー入ってます?)
このページではそんな(どんなだ?)ブランダンのアルバムレビューを軸に少々語ってみようかと思います。ちなみにここにのせたのは自分の持っているものだけで、スタジオワークの多いブランダンのことだから星の数ほど参加作品はあるかと思います。きっとその辺のディスコグラフィーの集大成を作っているファンのかたもおいででしょう。
1. Brandon Fields
ブランダンのソロアルバム。基本的にはペットとかフリューゲル・ホーンとの2管編成が好きなようで、ギターはあまり入れない傾向がある。アルトが中心だが、ソプラノ、テナー、ヤマハ・ウインドシンセなどもプレイしている。
The Other Side of the Story ('86)
 これが多分ブランダンのファーストアルバムだと思います。LAのフュージョン系マイナーレーベル(だと思う)のNovaからのリリース。いかにもLAフュージョンらしい音で、殆どがブランダンとウォルト・フラーによる2管フロントが中心。ギターは一曲目にゲストでロベン・フォードが参加しているのみ。バックは当時チック・コリア・エレクトリック・バンドに在籍していたジョン・パティトゥッチ(B)、デヴィッド・ガーフィールド(key)など。アルトの音色が美しく、この一枚で彼の魅力に引き込まれたものでした。
これが多分ブランダンのファーストアルバムだと思います。LAのフュージョン系マイナーレーベル(だと思う)のNovaからのリリース。いかにもLAフュージョンらしい音で、殆どがブランダンとウォルト・フラーによる2管フロントが中心。ギターは一曲目にゲストでロベン・フォードが参加しているのみ。バックは当時チック・コリア・エレクトリック・バンドに在籍していたジョン・パティトゥッチ(B)、デヴィッド・ガーフィールド(key)など。アルトの音色が美しく、この一枚で彼の魅力に引き込まれたものでした。
ヤマケンとこのアルバムとの出会いは全くの偶然。当時よくうろついていた関内のディスクユニオンのバーゲン棚で発見したLP。なんと¥380!! この頃ブランダンのことは全然知らなくて、ただジャケットのイラストと、ゲストにロベン・フォードが参加していると言うことで買いました。その後CDでも手に入れたのですが、これがなかなか高くて(¥2650!レコードの7倍?)何度も渋谷のHMV(今パチンコ屋になってしまったビルにあった頃)の売場をうろうろしたものですが、他の店で見かけなかったんで、しまいには根負けして買ってしまいました。(その後、店頭では見かけないなあ・・)
The Traveller ('88)
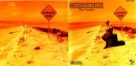 セカンド。これはDENONレーベルがNovaと契約したのか、国内盤でリリースされた。基本的に前作の延長線上の作風。前作よりもウインド・シンセのヤマハWX11(だったかな?7だったかな?)の使用が目立つような印象。しかし全体にタイトなフュージョン作品で、これも好きです。音色も好きな部類だし・・・。
セカンド。これはDENONレーベルがNovaと契約したのか、国内盤でリリースされた。基本的に前作の延長線上の作風。前作よりもウインド・シンセのヤマハWX11(だったかな?7だったかな?)の使用が目立つような印象。しかし全体にタイトなフュージョン作品で、これも好きです。音色も好きな部類だし・・・。
Other Voices ('89)
 以前PRISMの事務所を仕切っていた星野氏がレコーディング・エンジニアのアラン・ハーシュバーグ、キーボード奏者のデヴィッド・ガーフィールドと立ち上げたレーベル、Creachyからのリリース。スタッフが代わったせいかミュージシャンのちょっと入れ替わって、今回はヴォーカル(リー・リトナーのアルバムやライヴなどでお馴染みのフィル・ペリー)入りもあり。全体にちょっとポップな傾向が感じられる。ちょっと気にかかるのはサックスの音色が変わっていること。それがちょっと汚れている傾向だから・・・。
以前PRISMの事務所を仕切っていた星野氏がレコーディング・エンジニアのアラン・ハーシュバーグ、キーボード奏者のデヴィッド・ガーフィールドと立ち上げたレーベル、Creachyからのリリース。スタッフが代わったせいかミュージシャンのちょっと入れ替わって、今回はヴォーカル(リー・リトナーのアルバムやライヴなどでお馴染みのフィル・ペリー)入りもあり。全体にちょっとポップな傾向が感じられる。ちょっと気にかかるのはサックスの音色が変わっていること。それがちょっと汚れている傾向だから・・・。
(ちなみにCreachyの意味、知ってます? デヴィッドが野性味あふれる外観だもので、仲間は
"Creature" (生き物、というよりも「けだもの」みたいなニュアンスなんだろうか?)と呼んでいたのですが、本人はそれがすごく嫌で、それに気づいていた(たぶん)ジェフ・ポーカロがちょっとひねって
"Creachy" というニックネームに仕立てたらしいんですね、ですから
"Creachy" はデヴィッドのことなんです。
Everybody's Bussiness ('91)
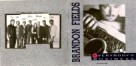 これは残念ながら日本の契約はなく、地元のNovaレーベルのみのようだが、同時にブランダンにとってはそのレーベルからの最後のリリースになったアルバムのようだ。前作のようなプロデュース過剰な傾向は皆無で、自分でやりたいようにやっている傾向。ちょっとおふざけが過ぎる傾向もないではないが、全体としてタイトなフュージョン作となっていて、私の中ではかなり好きな部類に属する。あちこちでブランダン自身のものと思われるちょっと不気味な声(エフェクトがかかっている?)が聴かれるのは
No thank you!! ガールフレンド(ワイフ?)相手に遊んだという感じの "Phone
Sax" (一文字違うと危ないストーカーの世界)もご愛敬としましょう。
これは残念ながら日本の契約はなく、地元のNovaレーベルのみのようだが、同時にブランダンにとってはそのレーベルからの最後のリリースになったアルバムのようだ。前作のようなプロデュース過剰な傾向は皆無で、自分でやりたいようにやっている傾向。ちょっとおふざけが過ぎる傾向もないではないが、全体としてタイトなフュージョン作となっていて、私の中ではかなり好きな部類に属する。あちこちでブランダン自身のものと思われるちょっと不気味な声(エフェクトがかかっている?)が聴かれるのは
No thank you!! ガールフレンド(ワイフ?)相手に遊んだという感じの "Phone
Sax" (一文字違うと危ないストーカーの世界)もご愛敬としましょう。
A Coffeehouse Christmas ('94)
 おお、ブランダンもクリスマス・アルバムを出すようになったか! ん? Positive Music? レーベルが変わったな。 雰囲気もちょっと4ビート風で今までのフュージョン主体とは違う傾向。 ま、クリスマスということは企画盤なので、あまり方針変更とかの参考にはならないが・・・。
おお、ブランダンもクリスマス・アルバムを出すようになったか! ん? Positive Music? レーベルが変わったな。 雰囲気もちょっと4ビート風で今までのフュージョン主体とは違う傾向。 ま、クリスマスということは企画盤なので、あまり方針変更とかの参考にはならないが・・・。
Brandon Fields ('95)
 Posotive Musicからの企画盤を除くと一枚目になると思われるアルバム。レーベルが変わってなにか変化は?という興味で聴いてみると、全体にソフトなトーンに支配されているのに気づく。メンバーはそれほど大きく変わっていないのだが、聞いたことのない名前のギタリストが全編通して入っていることに気づく。しかもこの人の音がジャジーでソフト。どうもこの影響が少なくないように思えた。
Posotive Musicからの企画盤を除くと一枚目になると思われるアルバム。レーベルが変わってなにか変化は?という興味で聴いてみると、全体にソフトなトーンに支配されているのに気づく。メンバーはそれほど大きく変わっていないのだが、聞いたことのない名前のギタリストが全編通して入っていることに気づく。しかもこの人の音がジャジーでソフト。どうもこの影響が少なくないように思えた。
ところで前々作の "Everybody's Business" でも登場したガールフレンド(ワイフ?)とおぼしき彼女(Gena)は名前(Kronstadt)からするとドイツ系の、素敵な女性なのだが、このアルバムではストリングスのアレンジとかコンダクトを担当している。ほほお、才色兼備、そんな感じですなあ。
Higher Ground ('97)
 ん?またレーベルが違う。今度はハイラム・ブロックも同じ時期に作品をリリースしていたVenus
Records。これは日本企画ですな。スティーヴィー・ワンダーのカバー集。最初そのリリースの話を聞いたとき、また日本企画でしょうもないものをこしらえてくれないだろうな? と少々不安になったものですが、雑誌のレビューを見たり、参加メンバーを見たりして、なんとか買う気になって手を出した。ミッチェル・フォアマン、ジョーン・ペニャ、ジェイムス・ハラーとなればやっぱり音を聴きたくなるってもんでしょう。
ん?またレーベルが違う。今度はハイラム・ブロックも同じ時期に作品をリリースしていたVenus
Records。これは日本企画ですな。スティーヴィー・ワンダーのカバー集。最初そのリリースの話を聞いたとき、また日本企画でしょうもないものをこしらえてくれないだろうな? と少々不安になったものですが、雑誌のレビューを見たり、参加メンバーを見たりして、なんとか買う気になって手を出した。ミッチェル・フォアマン、ジョーン・ペニャ、ジェイムス・ハラーとなればやっぱり音を聴きたくなるってもんでしょう。
で、内容ですが、・・・あ〜よかった、フュージョン系のカバーアルバムの中でもこれは比較的好きなアルバムにランクされました。
Brandon Fields & Strings ('99)
 ついにブランダンもウィズ・ストリングスをリリースしました。これまでにもアルバムの中にストリングスをからめた物を入れることは少なくなかったのだが、これは全面的にストリングスを入れた作品。で、ブランダンとストリングス、っていうとピンとくるのは例のGenaという女性。(ワイフかなあ?)。いましたいました。コ・プロデューサーになっているし、第一バイオリンだし、コンサート・マスターじゃないですか。おお、しかもスリーブの写真ではブランダンとハグしてますよ。やっぱワイフなんでしょうな、きっと。
ついにブランダンもウィズ・ストリングスをリリースしました。これまでにもアルバムの中にストリングスをからめた物を入れることは少なくなかったのだが、これは全面的にストリングスを入れた作品。で、ブランダンとストリングス、っていうとピンとくるのは例のGenaという女性。(ワイフかなあ?)。いましたいました。コ・プロデューサーになっているし、第一バイオリンだし、コンサート・マスターじゃないですか。おお、しかもスリーブの写真ではブランダンとハグしてますよ。やっぱワイフなんでしょうな、きっと。
2. Rippingtons featuring Russ Freeman & Russ Freeman (solo)
元祖スムース・ジャズと言って差し支えないプロジェクトですよね。(その割にはそのジャンルの全盛期である今は恵まれない境遇にあるのは何故?)
ブランダンはこのプロジェクトの初期に参加し、渡辺貞夫主催のライブ週間にリッピントンズのメンバーとしてデヴィッド・ベノワとともに来日したこともある。私しゃ、こんときにパーカッションのスティーヴ・リードの大胆なプレイとブランダンの社会の窓全開プレイに、じゃなくて美しい音色にほんとにびっくりしたもんでした。(第1部は思いっきり社会の窓全開だった(^_^;))
Nocturnal Playground (Russ Freeman) ('86)
。
Moon Riding (Cruise Control) ('86)
日本ではアルファ・ムーンのその名も "Baked Potato" レーベルから「クルーズ・コントロール」名義でリリースされた。これがアメリカでは何故か "Moon Lighting" となっていて、名義も違ったようだ。今から考えると豪華ゲスト参加で、デヴィッド・ベノワ、ケニー・ゴーリック(今のケニーG!)、ブランダン・フィールズ、ジミー・ジョンソン。バンド・メンバーはラスの他、グレッグ・カルカス(key)、ビル・ランファー(B)以外はスティーヴ・リード(per)、トニー・モラレス(ds)という後のリッピントンズレギュラーメンバー。
実質これがリッピントンズのデビュー作なんだろうな。ここではブランダンはあくまでゲスト扱い。サックスのトーンはまだちょっと煤けたというかそれほど透き通った感じではなかった。
のちにCDでもリイシューされたと思った。
Kilimanjaro (Rippingtons featuring Russ Freeman) ('88)
その後スムース・ジャズの牽引者となっていくラス・フリーマン率いるリッピントンズ名義ではこれが第一作かと思っている。アナログからCDへの移行期で、CD、LP併売が普通だった当時では珍しいCDのみのリリースだったことを思い出す。お恥ずかしいながらヤマケンもCDプレイヤー(パイオニアPD5010)を導入して間もない頃で一曲目のモロッコがかかったときのアナログとはまったく雰囲気の違うブライトな音に驚かされたことは今でも忘れられない。「あ〜、デジタルってこうなんだ〜」と思ったモンでした。
あの当初リッピントンズはLAのフュージョン系マイナーレーベル、Passport Jazzからリリースされていたが後に彼らも出世してグルーシン・ローゼン・プロジェクト(GRP)に引き抜かれ、このアルバムもGRPからのリリースとなって、ジャケットの下に当時のGRPのお約束だった "DIGITAL REMASTER" の文字が例のGRPロゴと共に追加されたものでした。ヤマケンは最初リリースされたものが後にCDプレイヤーをグレードアップ(DENON DCD−1610)したころにはデジタル臭さが耳につき始めたので、GRPになってマスタリングが変わっているのでは?と言う期待のもとに輸入盤で買いなおしました。結果は??う〜ん・・・。 ジャケットといえばリッピントンズのトレードマークとなったビル・メイヤー氏のジャズ・キャットが使われるようになったのはこのアルバムからでしたよね?
このアルバムでのメンバーはレギュラー的存在がヴィニー・カリウタ(ds)、ジミー・ジョンソン(B)、ブランダン(sax,flute)らで、キーボードは殆どラスが打ち込んでいた。
Tourist in Paradise (Rippingtons featuring Russ Freeman) ('89)
前作がバンド名義のわりにはセッション的にトラックごとに参加メンバーが代わっていた印象であるのに対し、こちらはバンド的にだいたいメンバーを固定していた。saxもほとんど(全部だったかな?)ブランダン。ちょうどこの時期にナベサダの "The Club" での来日ステージがあり、第一部はリッピントンズ単独、第二部は同じ時期に新作をリリースしたデビッド・ベノワとのジョイントによるものだった。私は曲の中で何度も慌ただしくエレクトリック(というかギター・シンセ・ドライバー)とタカミネのエレガットを持ち代えるラスのお忙しさ、存在感が大きくて曲の流れによっては革ものをスティックでたたいたり、シンバル系を素手で叩いたり、となんでもありのパーカッション(スティーヴ・リード)、のそっとした感じながら6弦フレットレスで超ハイテクプレイを何気なくこなしているベース(スティーヴ・ベイリー)とともに、第一部で社会の窓全開だったブランダンのパフォーマンスに、じゃなくってそのリリカルな音色でかつエネルギッシュなプレイにノックアウトされたもんでした。
3. Others
ブランダンのこの手の作品は要注意!特に日本企画のもの。日本のレコード会社がしょーもない企画なのにそこそこいい出来にしようとした時に何故か(たぶん)札びらで頬を叩かれがちなのがブランダン!ど〜してかなあ?そりゃ決まってるでしょ、って?う〜ん、まあそうなんだろうけど、そう思いたくない気持ちもあって・・・、ねえ?
Cuba /Karizma ('86)
。
Guitar Workshop in L.A. /V.A. ('88)
フュージョン系ギタリストのセッション・アルバムシリーズのLA版。当時ボズ・スキャッグスのバックをしていたテディ・キャステリッチ、マドンナ等のバックをしていたジェイムズ・ハラーの若手二人とバジー・フェイトン、ジェフ・スカンク・バクスターの4人をクローズ・アップしている。この中でブランダンはバジーとジェイムズのセッションに参加。名演と言うほどではないかな・・・。
(Forever in the )Arms of Love /Karizma ('89)
。
Los Lobotomys / Los Lobotomys ('89)
クリーチレーベルからリリースされた、ルークとデヴィッド・ガーフィールドが中心になったフュージョン系セッション・バンドのスタジオ・ライヴ盤。ジェフ・ポーカロ、カルロス・ヴェガ、ジョー・サンプル、ウィル・リーらも参加。
全体に当時のクリーチ特有のトーンを引きずっているところが唯一好きになれないが、それ以外は素晴らしいプレイで大好きな一枚。この後この名義のバンドはルークのソロ・プロジェクトみたいになっちゃって、あまり聴く気にならないが、聴いてみるといいかもしれない。
この中でのブランダンのプレイは吹っ切れてて華麗でかっこいいですぞ!
The Invitation from L.A. / V.A. ('90)
でました! どう考えても「バブル・マネーが有り余っていなかったらやるわけないだろ!」的企画。タスキの文句によれば、「素顔のままで」、「フラッシュ・ダンス」、「ウィー・アーザ・ワールド」等 グラミー賞受賞の名曲を集めたLA最新録音盤。デビッド・ベノア、バーナビー・フィンチ他、西海岸のトップ・ミュージシャンが参加。ブランダンは10曲中6曲に参加。参加ミュージシャンはタスキ表記、ブランダンの他にはランドゥ、カリウタ、ステューベンハウス、コンテなど。ま、金は使ってますね。
Nanno Songless / V.A. ('90)
これこそ日本がバブル・マネーにものを言わせた恥ずべき企画という類のものだろう。南野陽子(ナンノ)の曲をLAミュージシャンによるインスト作として仕立てたというもの。もともとアイドルの曲なんてキャラあってなんぼという程度のものが多くて、インスト化に堪えうるものはそう多くないと思うのだけど、これなんかその典型。とにかく曲が悪くて最後まで聞くに堪えない!。このアルバムに参加したことで私の中でのブランダンの格付けは一時、かなりダウンした。当時のジャズライフ誌のディスク・レビューの最後に熊さんが書いていた「ちょっとジャズ」のコーナーに載っていなかったら絶対知ることもなかったし、買うこともなかっただろう。ただ、そのコーナーにも書かれていたが、「パンドラの恋人」だけはバイオリンをメインに置いたアレンジが洒落ていて、唯一これだけが好きなトラックと言える。
Thinking of You (Alex Acuna & Unkowns) ('90)
。
Dichotomy (キー・ウェスト・サンセット) / Steve Bailey ('92)
。
Who Loves You - A Tribute to Jaco Pastrius / V.A. ('98)
。
I am the cat, ..........man" / David Grfield and the CATS ('98)
。
All the Way Live (Revisited) / Karizma
デヴィッド・ガーフィールドを中心としたLAスタジオ・ミュージシャンからなるプロジェクトであるカリズマの初来日時のライヴ盤。M.ランドゥ、C.ヴェガ、N.イースト、L.カストロ、L.クライマス、M.ミラーという布陣。渡辺貞夫さんのブラバス・クラブでの来日だったと記憶している。これはもともとデヴィッドがエンジニアのアラン、日本側の星野氏(もとPRISM所属事務所のボスだった人)と設立したCreachyレーベルからのリリースで日本では創美企画というところからリリースされていたと思った。出たときには他のCreachyレーベルのもののトーンを好きになれなかったので買わなかったが、その後手に入りにくくなってしまい、今回なぜかあれこれとCreachyのものが入手できるようになったのでこれも手に入れた。演奏はのっけから「如何にも!」という感じでなかなかファンを唸らすものがあるが、ん?聴き続けていくと何か飽きににたような印象が感じられてくる。何故??
Synergy /Dave Weckl Band ('99)
有能な若手を発掘する才に長けているチック・コリア、you know? あ、失礼しました。で、パティトゥッチ、スコヘン、ギャンバレとともにエレクトリックバンドに抜擢された若きテクニカル・ドラマーだったウェッケルもその後ソロとして様々な活動をした後、自身のバンドを持つこととなった。これはその二枚目。 このバンドが私にとって何よりも気になっていたのはギターにバジー・フェイトンがいることだったが、この二枚目ではさらにブランダンまでが参加するという大変なことになってしまっていた。う〜ん、このままずっと活動してくれたら・・・と思っていたが、コスト面とかの問題で次のアルバムではバジーは脱退していた。ブランダンは残っていたので、買おうかな・・・。
Mr. Clean / Mitchel Forman Quintet
私のかなり好きなフュージョン系ユニットであるMETROのキーボード奏者であり、それ以外にも様々なセッションに参加し、リリカルかつ瑞々しいプレイを聴かせてくれるミッチのクインテットによる’98のライヴ・アルバム。老舗の方のベイクド・ポテトでの演奏。
Live at the Baked Potato Volume one / Jeff Richman and V.A.
ジェフ・リッチマンというギタリストは日本ではなかなか評価が得られていない人の一人だと思う。かく言う私もCD一枚しか持っておらず、それもマイク・スターンら豪華ギタリストをゲストに迎えて作った作品だから、という不純な動機で買ったもの。(なぜかジェフのアルバムはそういう作り方をしているものが多い!) さらに言ってしまうと、その唯一持っているアルバムの印象も殆ど残っていない・・・。
これはそんなジェフがベイクド・ポテトの2号店を老舗のオーナーの息子さんがオープンするときのイベントとして考えた一連のライヴをレコーディングしたもの。リリースはかのシェラプネルのフュージョン系レーベルで、くせものが多いトーン・センター。残念ながらその2号店の方はもうクローズしてしまったらしい。
Live at the Baked Potato Volume two / Jeff Richman and V.A.
。
Full Moon Second / Buzz Feiten & Full Moon
ニュースは突然にやってくる! なんとバジー・フェイトンが「かの」伝説のバンド、フル・ムーンを再度結成し、アルバムを制作した。これは基本的には日本のレコード会社からの熱心な提案によるものだったようだが、バジーも結構乗り気で臨んだようだ。私としてはメンバーにsaxのブランダン・フィールズが入っているのもこの上なく嬉しい。思えばデイヴ・ウェッケル・バンドでレコーディング&ツアーを共にしたのが二人の初めての出会いだったようだが、バジーはこの時えらくブランダンのことを気に入ってしまったようだ。気のせいか収められている曲想もウェッケル・バンドでのバジー主導の曲のフンイキがある。
雑誌でのレビューを見ると、割とフル・ムーンに対する思い入れのある人が多いのだろうか、失望した旨を書かれている人もいたが、私はそういうこだわりでなく今のバジーやブランダンのプレイを楽しみたいので、非常に満足しています。ギターの音色もプレイも最高です。ヴォーカルもグッドよ。
ただ、ただですよ。やっぱ、言わしていただければならないのは「やっぱ、ニール・ラーセンでしょ?」ということです。スケジュールが合わなくて・・・、というのが理由になっていたが、そんなのなんとかしてよぉ!しかしキーボードで参加している人のプレイはオルガン主体でやっぱりニール色が見え隠れしている。今年の後半に日本に来てくれそうだけど、その時はニールがくるんじゃないのかな?と密かに期待してます。
ついでながら、裏ジャケ(上の写真でいうと左側)のデザインもフル・ムーンのファーストを知る人には泣かせますよね。